
大学受験の国語科目のなかでも、漢文は配点が低いと思われがちです。そのため、後回しにしてしまっている受験生は少なくないでしょう。
しかし、漢文は少ない勉強時間で得点源に転じやすく、戦略的に対策を進めればほかの科目に差をつけられる科目です。
本記事では漢文が短期間で成果を出しやすい理由を解説するとともに、基礎知識の身につけ方や演習のコツ、参考書の効率的な使い方を紹介します。
勉強時間が限られている受験生が効率よく得点を伸ばすにはどうすべきか、日々の勉強のヒントにしていただければ幸いです。
目次
大学受験で漢文が得点源になりやすい理由

後回しにされがちな漢文の勉強ですが、少しの時間を割くだけでほかの受験生に大きく差をつけられるため、頑張りがいのある科目です。
ここでは、その理由を具体的に解説します。
少ない勉強量で点数を取りやすい
漢文は短文中心であり、現代文の長文読解に比べて時間的負荷が少ないため、1日30分程度の演習でも効果が出やすい科目です。
さらに、漢字の読み下しや訓点の知識が定着すれば、長文の大意は驚くほどスムーズに追えるようになります。
1〜2ヶ月集中すれば基礎知識は十分に身につき、過去問や模試で実戦感覚を磨く時間も確保できるでしょう。
暗記項目が少ない
漢文の基礎となる漢字は大学入学共通テストおよび二次試験レベルで約200〜250字です。
古文や英単語に比べて覚える量が少なく、短期間で網羅できる量といえます。
また句法(返り点やレ点、再読文字など)のパターンも主に5種類ほどに分類でき、暗記と理解が双方で進みやすい構造です。
毎日少しずつ反復すれば、1ヶ月以内に漢文基礎がほぼ固まり、自信を持って演習フェーズへ移行できるでしょう。
古文の学習もしていると得点率がアップしやすい
漢文は後回しにしてしまっていても、古文はしっかりと勉強しているという受験生は少なくありません。
古文の学習をしていれば漢字の意味や助字の用法が腑に落ち、漢文の読解も自然とスムーズになります。
例えば「而」や「乎」といった助字の役割や返り点のルールを押さえておけば、句形の理解が格段にアップするでしょう。
さらに、古文単語や漢語慣用句の重複学習が語彙力を底上げし、限られた試験時間で効率的に得点を伸ばせます。
定番の句法パターンや文化知識を共有できる点も大きく、問題演習の応用力が飛躍的に伸びるでしょう。
問題がパターン化されている
漢文は出題パターンが明確なため、慣れるとどこを見れば解答につながるかがわかりやすく、得点につなげやすいです。
例えば、以下のようなパターンの問題が挙げられます。
・長文読解問題
・空所補充問題
・漢字の読みと意味
・慣用句・書き下しのルール
以上を踏まえ、対策の優先順位を漢字や句法→直読演習→応用演習と構成し、段階的に取り組めば、限られた時間でも効率的に高得点を狙えます。
学習のコツをとらえれば大きな得点源となる漢文ですが、それでも苦手意識が強い場合はプロ講師による適切なサポートを受けるのがおすすめです。
横浜予備校では、受験勉強に精通した講師による学習面談を通して、受験生それぞれに合った年間学習プランを計画しています。
さらに、独自に作成したオリジナルの参考書やテキストを生徒それぞれに提供しているのも大きな特長です。
市販の教材とは異なり入試に特化しているため、短期間で効率よく実力を伸ばすことができます。
実力の向上を実感することで、苦手意識の克服の一助となるでしょう。
無理のない学習プランを講師と一緒に考え、適切な参考書を使用することで、着実に苦手意識を乗り越えていきましょう。
まずは、無料相談や資料請求をお気軽にご利用ください。
大学受験の漢文で高得点を取るための勉強法

漢文の得点力を高めるためには、大きくわけて3つのステップで勉強していくのが効果的です。
ここからは、3つのステップでの勉強法を詳しく解説します。
重要漢字の意味を正しく暗記する
漢文の成否を分けるはじめの関門が重要漢字の習得です。
読み下しや訓点、送り仮名を含めた正確な意味と用例を覚えましょう。
覚えるべき漢字は共通テスト二次試験レベルで200〜250字ほどです。
頻度順にリスト化し、1日20〜30字ペースで暗記しましょう。
さらに、漢字帳や単語カードを活用し、通学時間や休憩時間にこまめに反復するのがポイントです。
書いて覚えるよりも、声に出して例文を読んで意味を確認するほうが記憶に残りやすいでしょう。
覚えた漢字は穴埋めや書き下し問題を通してアウトプットします。
インプットだけでは定着しないため、毎回5〜10題程度の確認テストを取り入れると効果的です。
句法の基礎を身につける

返り点やレ点、再読文字などの漢文特有の句法は知識がなければ読解が難しい一方で、1問あたりの配点が高く得点源にもなります。
基礎を固め、どのような場面でも自力で処理できるレベルを目指しましょう。
まず「返り点」や「レ点」のルールを一覧表でまとめ、例文を用いて実際に打ち込みながら意味を確認します。
また、再読文字は文脈によって解釈が変わるため、接続や呼応、強調の3パターンに分類して練習しましょう。
各テーマにつき10例文程度をノートにまとめると整理しやすいです。
さらに句法演習ドリルを利用し、設問付きの例文を1日5〜10文ずつ解きます。
句法確認→書き下し→現代語訳→再度句法チェックというサイクルを習慣化すると、自然とスピードが上がります。
演習で漢文を身につける

基礎知識を習得したら、いよいよ実践演習です。限られた時間のなかで限りなく大きな成果を出すには、質×量のバランスがポイントとなります。
演習用問題集や共通テスト過去問を用い、1題につき時間計測を行いましょう。
目安は現代文、古文と合わせた総合時間配分を意識し、漢文部分では10〜12分以内で解き切る訓練をします。
設問ごとに解答プロセスを図で整理することで、自分の思考パターンを可視化しましょう。
徐々に解答フローを短縮し、無駄な思考を削ぎ落とせるようにしていくと効果的です。
模試や過去問演習で出題形式に慣れたら、志望校の過去3年分は解いておきましょう。
独自の語句や句法パターンが頻出している場合があるため、年度ごとの特徴を把握し、弱点ノートにストックしていくとよいです。
学習のコツをおさえたとしても、ひとりで受験勉強を進めるのはどうしても不安を感じる場面に直面することも少なくありません。
そんなときこそ、横浜予備校にご相談ください。
横浜予備校では、受験指導に精通したプロの講師による個別指導を受けることができます。
一般的な個別指導塾のように大学生講師が中心となった授業ではなく、大手予備校での豊富な経験を持つプロ講師の授業を受けられるのが魅力です。
まずは無料相談や資料請求をお気軽にご利用ください。
漢文の参考書の効率的な使い方
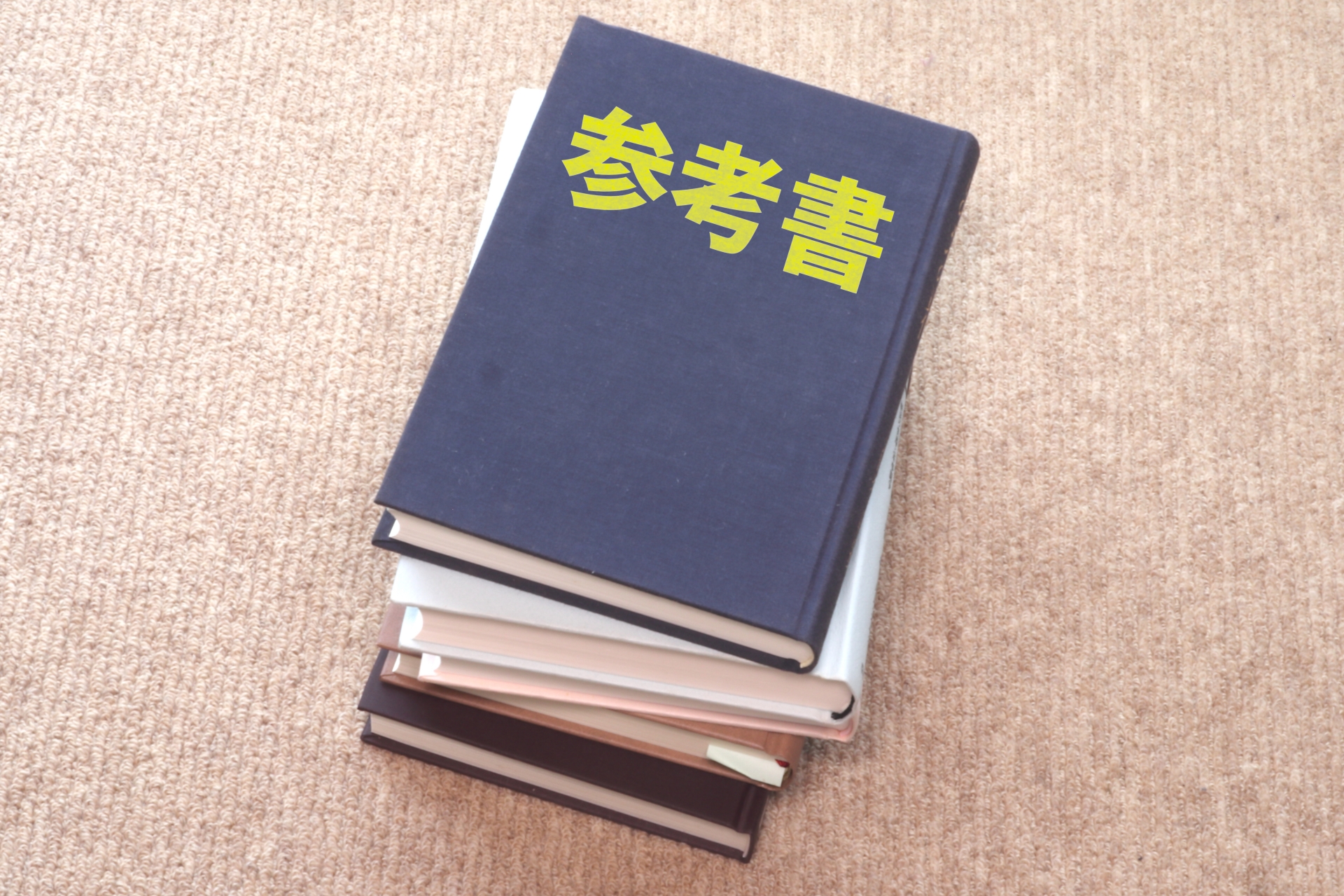
手持ちの参考書を1冊選んだものの、はじめの数ページを解いて満足してしまったり、復習が後回しになって成果に結びつかなかったりといった受験生は少なくありません。
以下からは、いつ、どのように参考書を使うかを明確にして基礎→定着→演習の3段階で効率的に活用するコツを解説します。
参考書を使い始める時期
参考書を使い始める時期の目安としては、高校2年生の冬〜3年生の春頃が効果的です。
漢文は後半戦でまとめてやろうとすると時間が足りなくなる科目です。早めに取り組むようにしましょう。
例えば、古文単語や英文法の基礎が固まってから、数学の模試が一段落したらなど、現代文や英語などの学習リズムを崩さない範囲でスキマ時間を利用しましょう。
共通テストや二次試験が迫る3年生の秋以降は、新しい参考書には着手せず、基礎固めに使った1冊を復習ツールとして活用するとよいです。
前年の模試や過去問で間違えた箇所を集中的にチェックしましょう。
参考書で基礎を固める
基礎知識を短期間で網羅できる参考書を活用して基礎を固めましょう。
漢字、句法のエッセンスが章立てで整理されている参考書は、はじめの1〜2ヶ月で一気に読み切るのがおすすめです。
各章末の確認問題にはきちんと取り組むようにしましょう。正解、不正解の理由をノートにまとめ、間違えた箇所は赤ペンで強調するのが効果的です。
同じ単元を3日ほど連続で繰り返し、記憶をより確かなものにしていきましょう。
また、間違えた漢字や句法パターンはノートにまとめ、別途復習タイムを設けます。
暗記の初期段階では無理に詰め込まず、毎日続けられる量に調整しましょう。
このように学習を進めることで、短期間で基礎を固めやすくなります。
演習問題を何度も解く
基礎知識を身につけたら、演習で知識を実際に使うフェーズに移行しましょう。
演習の効果は繰り返していくことで発揮されます。
1回解いて曖昧だった問題は赤シートで隠し、2回目、3回目と解き直しましょう。
3周目には、どの句法をどのように使ったかまで説明できるレベルを目指すと効果的です。
また、共通テストや志望校二次の漢文は年度ごとにフォルダ分けしましょう。
初回は読むだけに留め2回目は句法チェック、3回目は時間を計測しながら解答と、段階的に取り組むと効果的です。
さらに、週に一度自分でミニテストを作成しましょう。
くわえて間違えた問題だけを集めた弱点ノートを作り、試験形式で再テストして知識の抜け落ちを防ぐとよいでしょう。
大学受験の漢文におすすめの参考書

漢文学習を進めるうえでは、自分に合った参考書を選ぶことも得点力に大きな影響を与えます。
ここでは、基礎固めから実戦演習までのステップに合わせた3冊をご紹介します。
漢文早覚え速答法
こちらは、漢字や句法をなるべく早くマスターするための集中講義型参考書です。
頻出200字の漢字リストや返り点、再読文字など句法ルールを1ページ完結で網羅することができます。
各単元に確認問題がついています。
効果的な使い方としては、以下のサイクルがおすすめです。
・週3日ペースで1ユニットずつ学習
・各ユニット末のミニテストを解く
・誤答ノートに誤った漢字・句法の理由を記録して翌朝に復習
1ユニットずつ学習を進める際には、全15ユニットを5週間で一巡するようにしましょう。
基礎から解釈へ 漢文必携 五訂版
こちらは、初学者から中級者までをカバーする充実した例文集です。
平易な古典文からやや長文まで、ステップを踏んだ演習問題と丁寧な解答解説が充実しています。
句法別、テーマ別に問題が分類されていて、苦手項目に的を絞って学習できます。
句法項目ごとに例文→解説→練習問題をセットで学習したら、週に1テーマを集中してマスターしていく使い方がおすすめです。
テーマ学習後には、総合問題(章末演習)に取り組み、自力読解を確認しましょう。
漢文道場 入門から実践まで
こちらは、入門レベルから難関大対策までを1冊で完結する演習特化型問題集です。
難易度別に1~5までレベル分けされた長文問題が収録されており、志望校のレベル感に合わせた演習ができます。
まずレベル1〜2を完全制覇し、基礎力を固め、レベル3〜4で応用演習を進めて苦手分野を洗い出すのが効果的な使い方です。
レベル5は志望校の難易度に合わせて挑戦しましょう。
模試直前期の実戦演習として活用するのがおすすめです。
大学受験で漢文を得点源にしたいなら
ここまでご紹介した自力学習プランだけでも十分に得点力を伸ばせますが、さらに短期間で安定して高得点を狙うには、プロのサポートが大きな後押しになります。
特に漢文はわからない箇所を放置すると一気に得点源から遠ざかる科目です。
横浜予備校では、各生徒それぞれに最適なカリキュラムを作成し、志望校に合わせた戦略的なプラン作成を行っています。
生徒の学力を詳細に分析し、無理なく効率よく得点アップを目指すことが可能です。
さらに、少人数制(1クラス平均2名)や個別指導を徹底しているため、各生徒の学力や目標に合わせた細やかなサポートを提供することができます。プロのサポートがあれば、努力するための道筋を早めに見定めることができます。
成績が伸び悩んでいると感じたら、まずは横浜予備校の無料相談をご利用ください。志望校の出題傾向を踏まえた合格に向けた適切なルートを、講師一丸となって提案いたします。












