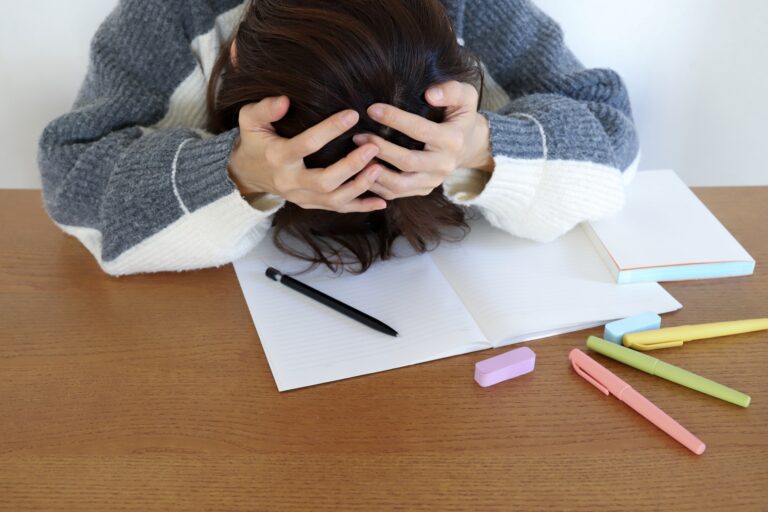大学入試科目として地理を選択した方のなかには、どのように勉強すればよいか不安を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
地理はほかの社会科科目と比べ暗記量が少ないとされ、取り組みやすい科目と見なされがちです。
一方で、地理は資料を読み解く力が求められることから、正しい勉強法が重要です。
この記事では入試科目としての地理の特徴や勉強法、参考書の使い方を詳しく説明します。
目次
大学受験の地理科目の特徴と立ち位置

地理を入試科目として選択した方のなかには、点数が安定せず不安を感じている方もいらっしゃるかもしれません。
地理はほかの社会科科目より暗記量が少なく楽な科目ととらえられがちですが、資料を読み解く力や考察力を身につけなければ点数を伸ばしにくい科目でもあります。
正しい勉強法を理解するためには、まず地理の特徴を知ることが重要です。
ここではいくつかポイントを挙げて特徴を解説します。
系統地理と地誌の違い
地理科目は大別すると系統地理と地誌のふたつに分けられます。
系統地理は気候、地形、文化などテーマ別の視点から世界全体の地理を考察する分野です。
一方、地誌では世界全体を地域や大陸に分けてその特徴を学習します。
受験における系統地理と地誌の重要度を比較すると、系統地理の方が重要度、難易度ともに高いです。
なぜならば地誌は系統地理の正しい学習により自然と答えを推測できるようになるからです。
このことから地理で点数を伸ばすには、系統地理と地誌の違いを理解し、正しい勉強法・順序で学習することが鍵になります。
暗記量が少ない
地理はほかの社会科科目より暗記量が少ないといわれていますが、それは正しくもあり誤りでもあります。
地理の学習内容はとても幅広く、それをすべて丸暗記しようとすれば歴史科目と同じくらい膨大な量になることは明白です。
しかし、地理の範囲を理解する部分と暗記する部分に分けて学習することで暗記量を大幅に減らせます。
このことから、地理は暗記量が少ない科目とは一概にはいえず、暗記量をできるだけ少なく抑えて地理の点数を伸ばすには学習のコツが必要であるといえます。
点数がとりにくい

地理は暗記科目に比べ、試験時間中に考える時間が長くなります。
これは出題される問題に思考力や考察力を必要とするものが多いためです。
長時間の思考を続けるには高い集中力も必要です。
物事の論理的思考に苦手意識がある方や集中力を長時間持続させることが難しい方にとっては、地理は暗記科目より点数がとりにくい科目といえるでしょう。
国公立理系志願者が受けやすい
地理は学習のプロセスの点で理系科目に通じる部分が大きく、理系の受験生が受けやすい科目です。
地理で点数を伸ばすには、論理的思考に基づいた考察やデータ分析がとても重要であり、これは理系受験生が得意とする部分でもあります。
効率的に学習することで暗記量を抑えられ、ほかの科目に時間を割ける点も、理系受験生にとって地理選択の利点です。
資料から背景を読み解き考えることが必要
地理科目の入試問題として特徴的なもののひとつに、資料の読み取り問題があります。
資料の読み取り問題では貿易や気候など、世界のさまざまな数値がグラフや図を用いて提示され、その内容から回答を導き出すことが必要です。
暗記だけでは解けない思考力重視の問題が増えており、対応力が点数を左右する傾向にあります。
大学受験で役立つ地理の正しい勉強法

ここまで大学受験における地理の特徴を解説しました。
地理の点数を伸ばすには、知識の暗記だけではなく内容の理解とそれに基づく思考力が重要です。
ここからは地理科目に対する理解を深めるための正しい勉強法を4つ紹介します。
地図を見ながら理解する
地図を用いた勉強法を取り入れると、参考書の内容の理解を深めることができます。
地図には大陸や国の位置関係だけでなく、山・川・標高なども示されており、視覚的に地域の特徴を把握できます。
地域の特徴を大まかに把握するだけで、川の位置や標高の高さから人々の生活と産業の発展や気候など、理解のためのアンテナを伸ばしやすくなるでしょう。
模試を利用してアウトプットできるようにする

linear-gradient(transparent 80%, #66ccff 80%);">知識をアウトプットする訓練はとても有効な勉強法です。
受験勉強というとひたすら知識を蓄えるインプットの学習に力を入れがちです。暗記科目ではそれも重要な要素ですが、地理の点数を安定させるには蓄えた知識をアウトプットする力を養う必要があります。
思考力が問われる問題では出題内容にあわせて、蓄えた知識を記憶の引き出しから取り出して、適切な回答を導き出す作業が必要です。
この作業は繰り返しの訓練により精度とスピードを高めることができます。
模試は知識の活用力を高める訓練として、とても有効です。積極的に活用しアウトプット力を養いましょう。
わからないことは調べる
地理の学習を進めていくと、なぜ?という疑問がいくつも出てくることがあります。
疑問はそのままにせず、徹底的に調べましょう。
自分で調べて答えを見つける作業は、ただ参考書を読むよりも格段に知識を深めます。
調べる方法は参考書以外にも辞書やインターネット、ほかの科目の教科書など、さまざまなものを利用しましょう。
調べる過程が記憶の定着を促し、知識を確かなものにします。
疑問が出てきたときこそ、地理の理解を深める絶好のチャンスです。
資料問題はしっかり解いておく
問題集に出てくる資料問題はしっかり解いておきましょう。
読み解く力が求められる資料問題では、過去問の回答を暗記しただけでは新しい問題を解くことはできません。
問題を繰り返し解いて解法を理解することで、初めて見る問題にも対応できるようになります。
大学受験の地理には応用力が求められる?

前述のように、大学受験の地理では応用力が不可欠です。
どれだけたくさんの知識を暗記してもそれを応用できなければ、思考力・考察力が求められる問題で力を発揮できません。
地理の点数を安定させるためには、なぜそうなるかを考え、複数の資料・データを比較して分析する力が重要です。
今まで知識のインプットばかりに力を入れる学習を行ってきた方は勉強法の見直しが必要かもしれません。
参考書や問題集を使った学習だけでは、思考の深さや知識の応用力を十分に鍛えられないことがあります。
特に地理のように暗記と論理を融合させる科目では、独学のままでは得点が安定せず、限界を感じる受験生も少なくありません。
横浜予備校では、こうした課題に対して的確なサポートを提供しています。
受験指導のプロ講師による直接指導のもと、生徒一人ひとりのつまずきや理解不足を丁寧に掘り下げ、着実な応用力の養成を図ります。
また、横浜予備校独自の取り組みとして「プレゼン授業」を導入しています。
受験生自身が講師に対して学習内容をプレゼンすることで、インプットした知識を整理・定着させ、実際の入試で使える力へと昇華させる学習法です。
知識のアウトプットを通じて論理的思考と表現力が鍛えられ、記述問題や難問への対応力が大幅に向上します。
地理の得点を安定させたい、応用力に課題を感じている、といった悩みをお持ちの方は、ぜひ横浜予備校の無料相談をご利用ください。
ノートや参考書を活用した地理の学習のコツ

地理の理解を深めて効率的に学習するには、ノートの取り方や参考書の選び方にもコツが必要です。
今日から取り組める4つの具体的な方法を紹介します。
ノートの余白は多めに作り白地図を貼る
地理を効率よく勉強するために理解を深めやすいノート作りを心がけましょう。
余白を多く作ると後から疑問が湧いてきたときに調べた情報を書き込むことができ、記憶の定着に役立ちます。
このとき、調べた内容を丸写しするのではなく自分の言葉として噛み砕いて書き込むことが大切です。
また白地図の利用は学習内容を視覚的に把握しやすくなるため大変有効です。
学習した内容を白地図に書き込むと、地域の特徴が整理されて頭に入りやすくなります。
参考書は背景のわかりやすいものを使う
参考書の選び方で重要なのは、学習内容の背景がわかりやすく記載されているものを選ぶことです。
知識ばかりが書かれている参考書を使用すれば、どうしても学習がインプットに偏りがちになります。
実際の入試問題で蓄えた知識を応用するには、知識の背景まできちんと理解することが重要です。
また、いくら背景が丁寧に書かれていても、その説明文が読みにくかったり難しすぎたりすると真価を発揮できません。
自分の理解力のレベルにあった読みやすい参考書を選びましょう。
参考書は出版日の新しいものを選ぶ
受験問題の出題傾向は年々変化しています。実際に、2025年からは共通テストにこれまでの地理A・地理Bに代わって地理総合・地理探求、地理総合・歴史総合・公共が導入されました。
昔と比べて思考力や考察力を重視する問題が増えていることは前述のとおりです。
さらに地理は社会科科目のなかでも時事問題の影響を受けやすい科目であり、新しい社会問題を把握しておくことが重要です。
古い参考書を使用すると近年の世界情勢などへの理解が不十分になる可能性があります。
参考書は出版日が新しく、情報がアップデートされたものを選ぶのが鉄則です。
苦手な分野はどこなのか理解しておく
問題集や過去問を解いた後、間違えた問題をそのままにしていないでしょうか。
間違えた問題を見直して自分の苦手分野を把握することはとても効率のよい勉強法です。
受験当日までの勉強時間は有限です。自分がすでに理解している部分を繰り返し解くことに時間を割くのではなく、苦手な部分を重点的に学習する方が効率よく点数を上げる効果が期待できます。
間違えた問題はノートにまとめ、後から見直せるようにしておきましょう。
独学で学習を進めていると、自分の苦手分野を客観的に把握するのが難しく、同じようなミスを繰り返してしまうこともあります。
模試や過去問で「またこのパターンを間違えた」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
横浜予備校には、大手予備校での指導経験を持つ一流のプロ講師が多数在籍しています。
授業は1対1から最大でも1対4までの少人数制(1クラス平均2名)を徹底しており、生徒一人ひとりのつまずきや学習ペースに合わせたきめ細かな指導が可能です。
特に、苦手分野の洗い出しと克服に強みがあり、過去の模試結果や日々の演習から誤答傾向を丁寧に分析。
曖昧な理解や思い込みによるミスを根本から見直し、着実に得点力を伸ばしていきます。
「自分では何が苦手かわからない」「どこから対策すればよいか迷っている」と感じている方もご安心ください。
横浜予備校では、受験生一人ひとりに合わせた最適な学習戦略を専属コーチが一緒に考え、実行をサポートします。まずはお気軽にご相談ください。
大学受験で地理を選択して高得点を取るには

この記事では大学受験における地理科目の特徴や、高得点を目指すうえで身につけるべき力について詳しく解説しました。
地理で高得点を取るには知識をインプットするだけではなく、思考力・考察力を高めて蓄えた知識を応用できるよう訓練を重ねることが重要です。
独学での受験勉強では、気が付かないうちに非効率な勉強法を続けてしまい、努力が点数に結びつかないリスクがあります。
地理の勉強法に少しでも不安がある方は、限られた時間を最大限に活かすためにも、プロの指導を受けることをおすすめします。
横浜予備校では、各生徒の理解度や模試の結果をもとに詳細な学力分析を行い、それぞれに最適なカリキュラムをオーダーメイドで作成しています。
暗記に偏りがちな地理学習も、プロ講師による丁寧な解説と効果的なアウトプット指導によって、思考力・応用力をバランスよく養うことが可能です。
さらに、地理では「覚えたのに得点できない」「模試で点数が安定しない」といった悩みを持つ受験生も少なくありません。
横浜予備校では、原因となるインプットとアウトプットのギャップを明確化し、演習や解説の中で一つひとつ解消していきます。
プロ講師のサポートを受けながら、効率よく高得点を目指したい方は、まずは無料相談をご利用ください。あなたに適切な学習方法と戦略をご提案いたします。