
受験生の子どもに対して、つい言ってしまった一言で空気が悪くなった経験はありませんか。
ちょっとした一言がきっかけで「励ましたつもりだったのに落ち込んでしまった」と感じる保護者の方も少なくありません。
本記事では受験期に避けたいNGワードや行動の具体例を紹介し、子どもを追い詰めずに支えるための接し方を解説します。
目次
受験生へのNGワード
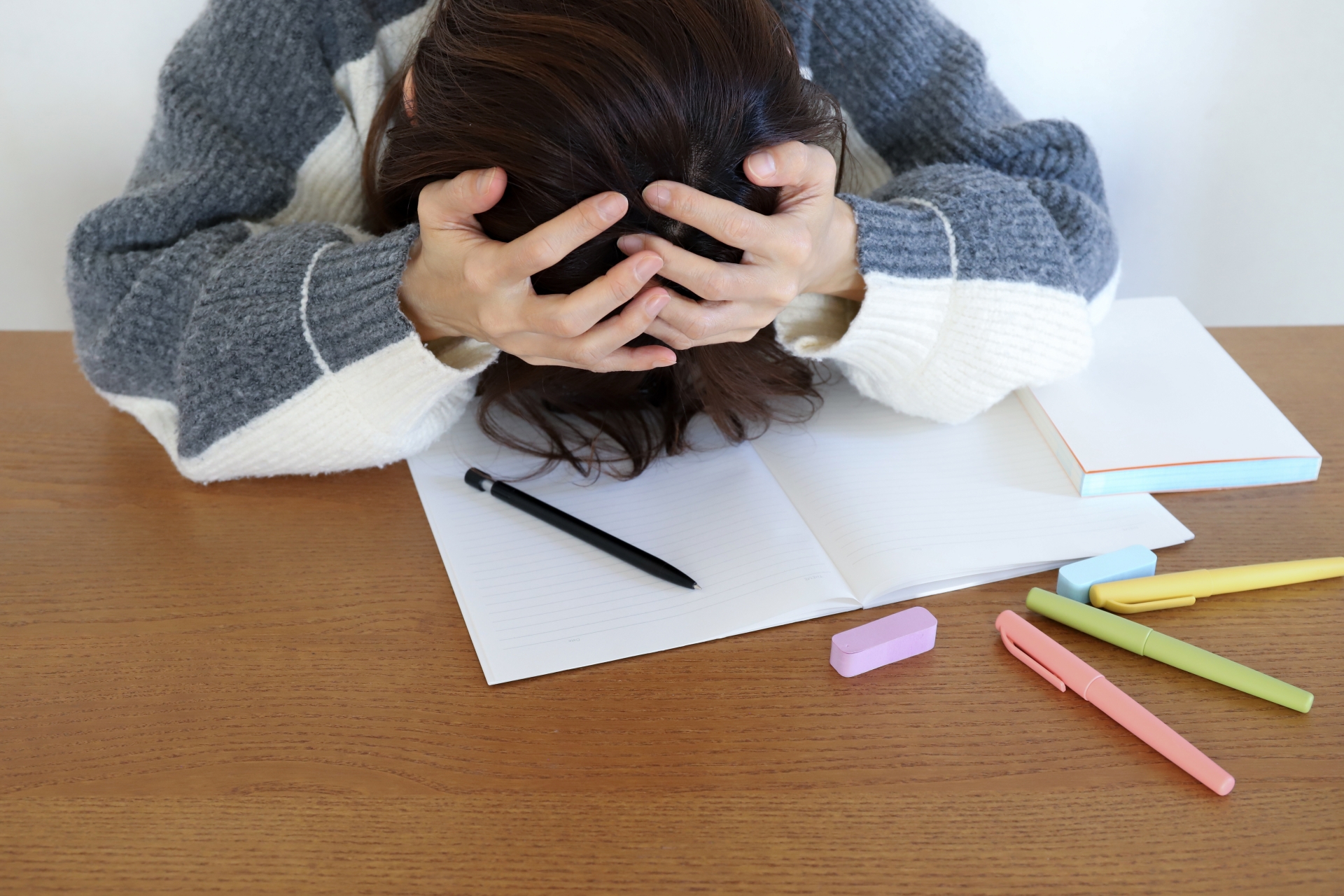
受験生を持つ保護者のなかには、勉強を頑張ってほしい思いから、強い言葉をかけてしまうことがあります。
しかし、親にとっては励ましのつもりでも、受験生にとってはプレッシャーとして受け取られてしまうことがあります。
ここでは受験生のやる気を削いだり、自信をなくしたりする、6つのNGワードを見ていきましょう。
不安を煽る言葉
「今のままで大丈夫なの?」などの不安を煽る言葉は、受験生の不安をさらに強めてしまう可能性があります。
励ますつもりでも、本人には追い詰められているように感じられることも少なくありません。
受験期は精神的に不安定になりやすいため、不安を煽るよりも「困っていることある?」など具体的な行動につながる声かけが効果的です。
勉強することを強いる言葉
「勉強しなさい」という言葉は口にしてしまいがちですが、受験生には強いプレッシャーとなることがあります。
親の立場からは、心配や期待の表れであっても、子どもにとっては責められているように感じてしまうことがあります。
そのため、声をかけるときは「今日は順調?」など状況を確認するような言い方にすると、相手の主体性を尊重しながら見守る姿勢が伝わるでしょう。
人格や能力を否定する言葉
人格や能力を否定する言葉は、受験生の自己肯定感を大きく傷つける恐れがあります。
人間性や能力そのものを否定するため、心に強く残ってしまいます。
大切なのは、過程や努力に目を向けて声をかけることです。
「頑張ってるね」や「前より理解が深まってきたね」などの肯定的な言葉をかけることで、受験生の自信につながります。
人と比べる言葉
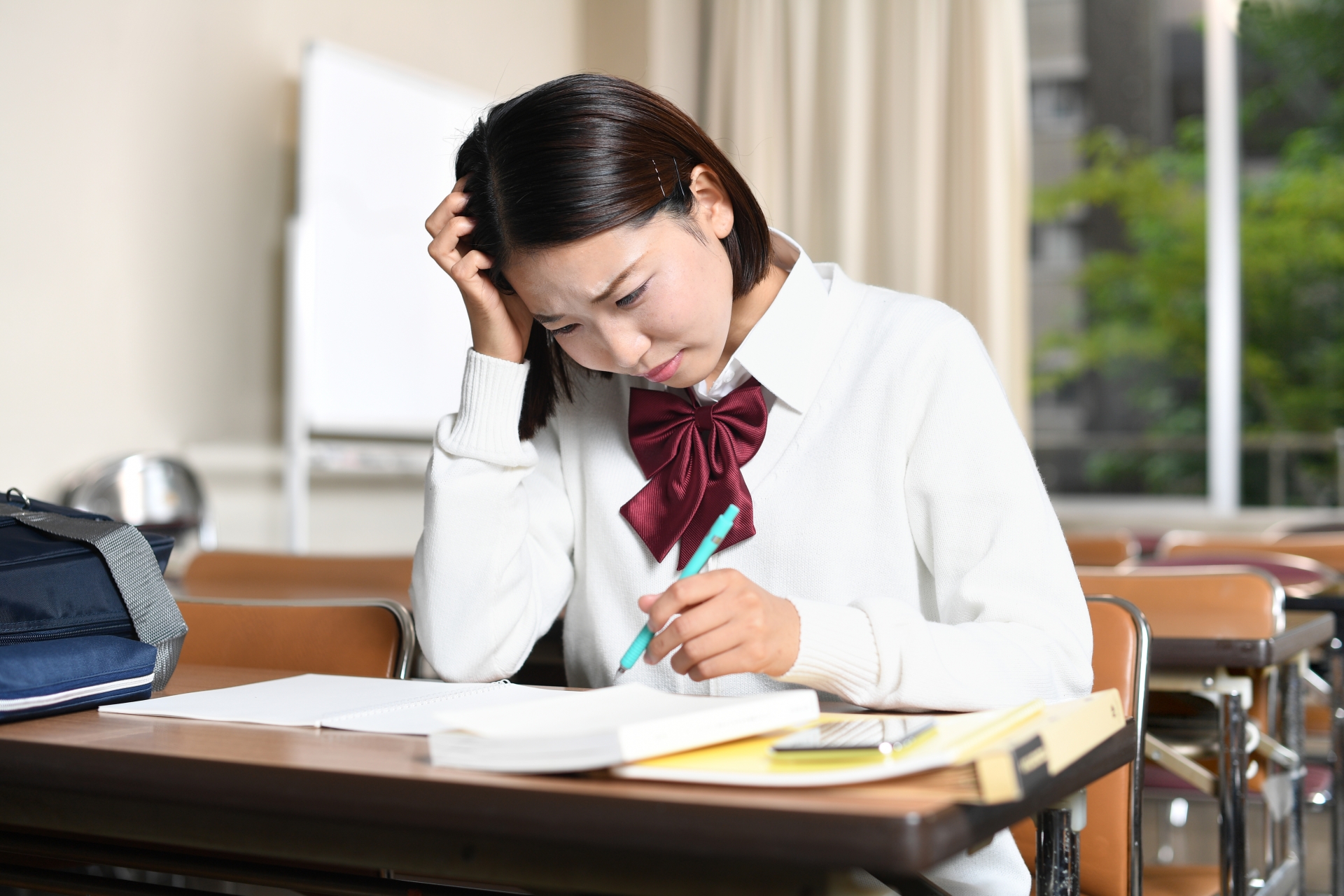
他人と比較するような発言は、受験生の自尊心を大きく傷つける恐れがあります。
「ほかの子はもっとできている」など、無意識のうちに出る言葉でも、本人にとっては強いプレッシャーとなることがあります。
受験生は不安や焦りを抱えているため、他人との比較が加わると、自分は劣っているのではないかと思い込んでしまいがちです。
声かけの際は、過去の自分と比べて前進できている点を認める言葉が効果的です。
合否の結果を意識させる言葉
合否に言及する発言は、受験生に大きなプレッシャーを与えます。
結果だけを重視されていると感じさせ、学習意欲の低下や自信喪失につながる恐れがあるでしょう。
特に受験直前や模試の後など不安定になりやすい時期にこうした言葉をかけられると、失敗を恐れ、集中力が乱れることもあります。
そのため、合否の話題はなるべく避け、プロセスを認める声かけが大切です。
ご褒美や罰でやる気を出させようとする言葉
ご褒美や罰でやる気を出させようとする言葉は、逆効果になることがあります。
本人の内発的なやる気を育てにくく、プレッシャーや不安の原因になってしまいます。
受験勉強は長期戦のため、目先のご褒美や罰では持続的なモチベーションを保ちにくいです。
成果に対するご褒美ではなく、日々の努力や継続に目を向けて声をかけることが大切です。
受験期のお子さんを支える保護者の方のなかには、「どう声をかければいいのか分からない」「励ましたつもりが逆効果だった」と悩まれる方も多いのではないでしょうか。
本質的なやる気を引き出すためには、家庭だけでなく第三者の視点や専門的なサポートが効果的なケースもあります。
横浜予備校では、学習指導だけでなく、親子間のコミュニケーションやメンタル面での不安にも丁寧に対応しています。
「何から話せばよいか分からない」「親としてどうサポートすればよいか知りたい」そんな時こそ、第三者の知見が新たな気付きにつながるでしょう。
まずは無料相談をご活用ください。保護者の方も、一人で悩まず、専門家の知恵を味方につけましょう。
受験生へのNGワードの具体例

「自分は子どもを傷つけるようなことは言っていない」と感じていても、無意識のうちに受験生を追い詰めているケースは少なくありません。
何気なく口にした一言が子どもにとっては強いプレッシャーとなり、自信をなくす原因になることもあります。
ここからは、保護者がよく使いがちな5つのフレーズを具体的に取り上げ、どう言い換えればよいのかを解説します。
「このままだと合格は厳しいよ」
「このままだと合格は厳しいよ」という言葉は、受験生にとっては突き放されたように感じる表現になります。
たとえアドバイスのつもりであっても、本人の努力を否定する印象を与えかねず、自信を失う原因となってしまうこともあります。
そのため、受験生に対しては、具体的なサポートや成長を促す言葉が効果的です。
例えば「最近頑張ってるね」や「一緒に見直してみようか」など、努力の過程に目を向けた声かけをすると、受験生は前向きな気持ちを保ちやすくなります。
「勉強しなさい」
勉強を指示する言葉は、受験生にとって命令や強制と感じてしまうことがあります。
例えば「早く机に向かいなさい」や「今すぐやらないと間に合わないよ」などの言い方は、本人のタイミングや気持ちを無視しているように受け取られ、かえってやる気をそいでしまうこともあるでしょう。
また勉強を指示する言葉が繰り返されると、子どもは信用されていないと感じ、親子の信頼関係を損なう可能性もあります。
声をかけるときは「今日は何時間勉強をする予定?」のように、本人の計画を尊重しながら寄り添う言葉が効果的です。
「そんなところ受けるんだ」

志望校に対する否定的な言葉は、受験生の自信を大きく揺るがせてしまうことがあります。
例えば「その学校じゃ将来苦労するよ」や「もっと上を目指せば」といった言葉は、本人の意思を軽んじられたように感じさせ、モチベーションの低下を招く恐れがあります。
進路の選択肢は偏差値や知名度だけで決めるものではなく、本人の興味や適性、将来像によって選ばれるものです。
親が否定から入ると、子どもは自分の選択を受け入れてもらえないと感じ、進路について主体的に考える意欲すら失いかねません。
そのため「どうしてその学校にしたの?」と関心をもって聞くことが、信頼関係を築くうえでも効果的です。
子どもの選択を尊重し、まずは耳を傾ける姿勢が、失敗を恐れず挑戦できる環境づくりにつながります。
「受かるといいね」
一見すると応援の言葉にも思えますが、受験生にとってはプレッシャーとなることがあります。
例えば、親が「受かるといいね」と声をかけた際、子どもは合格しなければがっかりされるかもと感じてしまうことがあります。
こうした言葉が続くと、努力の過程を見てもらえていないと感じ、モチベーションの低下を招く恐れもあるでしょう。
また、結果だけを評価されていると感じると、日々の頑張りが報われない気持ちになることもあります。結果だけではなく、プロセスをねぎらう言葉をかけましょう。
「いくらお金がかかってると思ってるの」
金銭に関わる発言は、受験生にとって自分の存在や努力が費用と結びつけられたように感じ、強い罪悪感や重圧につながる恐れがあります。
大切なのは、金銭的な負担を押し付けるのではなく、応援している気持ちを言葉で伝えることです。
「応援しているよ」といった声かけの方が、受験生の心の支えになります。
とはいえ、親としてどのように気持ちを伝え、どう支えるべきか悩むこともあるはずです。
無理に励まそうとして空回りしたり、感情的になってしまったりすることもあるでしょう。
そんなときこそ、第三者である専門家の力を借りることが有効です。
横浜予備校では、受験生だけでなく保護者の方にも寄り添い、家庭内での関わり方や声かけの工夫についても個別にサポートしています。
無料相談では、専門スタッフが一人ひとりの状況に応じてアドバイスを行い、「どこまで口を出していいかわからない」「つい感情的になってしまう」といった不安にも丁寧に対応します。
ご家庭での接し方に迷ったら、まずは一度無料相談をご利用ください。
親御さん自身が安心してサポートできるよう、全力でお手伝いします。
受験生へのNG行動

受験生との関わりでは、日々の態度や行動も大きな影響を及ぼします。
良かれと思って行っている行動が、子どもにとってはプレッシャーになったり、逆に無関心と受け取られたりすることも少なくありません。
ここからは、具体的に避けるべき3つのNG行動を解説します。
過度に干渉する
受験生の行動を逐一チェックし、勉強方法や時間の使い方に細かく口を出すと、本人の自主性を奪ってしまう可能性があります。
例えば「今何やってるの?」や「そのやり方で大丈夫?」と繰り返し聞かれると、子どもは信頼されていないと感じてしまい、ストレスが蓄積されやすくなります。
受験生は自分のやり方で成長しようとしている段階です。
親の役割はアドバイスを押しつけることではなく、適度な距離感のあるサポートが、子どもにとって心強い支えとなります。
無関心な態度をとる
親が無関心な態度を示すと、受験生の子どもは自分は応援されていないと感じ、モチベーションの低下を招いてしまうことがあります。
例えば模試の結果や志望校の話に反応が薄いと、子どもは関心を持たれていないと感じ、孤立感を深めてしまうこともあるのです。
大切なのは過干渉ではなく、見守りながら関わる姿勢です。
「お疲れ様。最近、頑張ってるね」といった一言で、十分に関心と応援の気持ちは伝わります。
自分の価値観を押し付ける
親が自分の価値観を押し付けると、受験生は自分の意見を尊重されていないと感じてしまうことがあります。
例えば「この学校の方が将来安定しているよ」や「自分の頃はこうだったから」といった発言は、子どもの意思や興味を否定されたように受け取られることがあります。
大切なのは、親の考えを一方的に伝えるのではなく、子どもの思いや選択をいったん受け止める姿勢です。
「どうしてその学校に興味を持ったの?」と問いかけることで、子ども自身が進路について主体的に考えるきっかけになります。
信頼関係を築くには、子どもの考えに耳を傾け、共に考えるスタンスが効果的です。
受験生を持つ親の役割

受験生のわが子を目の前にすると、ついアドバイスや叱咤激励をしてしまいがちですが、親の大切な役割は子どもが落ち着いて勉強できる環境を整えることにあります。
受験は長く精神的な負荷も大きいため、家庭が落ち着ける場所であることは子どもにとって大きな支えとなります。
大切なのは、子どもを信じて見守る姿勢です。
勉強の様子が気になっても、まずは本人のペースを尊重しましょう。
子どもが何事も心配せず、努力できる家庭環境を整えることが、親にしかできない重要なサポートとなります。
受験生にかける言葉には配慮して合格をサポートしよう

家庭でどのような言葉をかけられるかは、学習意欲や精神状態に大きく影響します。
比較や否定などの言葉はプレッシャーとなることがありますが、過程を認める声かけや態度は、受験生の心を支える大きな力になります。
大切なのは、親が見守り、信じる存在としてそばにいることです。
適切な距離感を保ちつつ、必要なときだけそっと背中を押してあげることが、子どもの本来の力を引き出すきっかけになるでしょう。
しかし、お子さんの性格や状況によっては、どのように声をかければよいのか悩んでしまうこともあるでしょう。
そんなときは、家庭だけで抱え込まず、第三者の力を借りることも選択肢の一つです。
横浜予備校では、受験生本人はもちろん、保護者の方の不安や悩みにも丁寧に寄り添うことを心がけています。
お子さんの性格や志望校、学習状況を踏まえたアドバイスに加え、「家庭でどのように声をかけるのがよいか」「どのような距離感が適切か」といった保護者目線の悩みにも、お応えします。
「専門家のサポートも取り入れてみたい」と感じた方は、ぜひ一度、横浜予備校の無料相談をご利用ください。
ご家庭での関わり方に迷っている方にとって、大きなヒントが得られるはずです。











