
大学受験を控えて「科目選択はどのようにすればよいだろう?」「将来就きたい仕事もまだ決まっていないけど、どの科目を選べば損しないかな?」とお悩みの学生さんもいらっしゃるのではないでしょうか。
高校1年生や2年生の皆さんにとって、大学受験の選択科目は将来の可能性を広げることもあれば、逆に狭めてしまうことにもなりかねません。
特に、まだ志望する大学や学部が明確に決まっていない段階では、何となく得意・不得意で選んだり友人の選択に流されたりしがちです。
この記事では、不安を抱える高校生や保護者の皆さまのために大学受験の科目選択で失敗しないためのコツ、大学入学共通テストの仕組みや注意点を解説します。
科目選択のための明確な判断軸を身につけ、後悔のない決断を下すために、ぜひ参考にしてください。
目次
大学受験の科目選択で失敗しないためのコツ

大学受験の科目選択は、単にテストを受ける教科を決めるだけではありません。
志望校合格に向けた学習計画の基本となり、大学入学後の学びや将来のキャリアにまで影響を及ぼす可能性があるため、慎重に選択する必要があります。
この章では、大学受験の科目選択で失敗しないために押さえておくべきコツを4つ紹介します。
ポイントを意識するだけで選択の精度は高まるため、根拠なく決めてしまう前に、一度立ち止まって自身にふさわしい選択肢をじっくり考えてみましょう。
志望大学の出願条件となる科目を確認する
科目選択で重要なのは、志望大学や興味のある学部や学科が指定している受験科目の確認です。
特に国公立大学を目指すのか私立大学を目指すのか、また文系なのか理系なのかによって、必要な科目は大きく異なります。
例えば、理系の学部では理科で物理や化学の選択が必須となっている大学が多く、これらの科目を履修していなければ出願すらできません。
まだ志望校が決まっていない方も、まずは大学の公式Webサイトや文部科学省のポータルサイトなどで入試要項を調べてみましょう。
学校で勉強している科目を選ぶ
大学受験の科目は、基本的には高校の授業で勉強している科目から選択するのがよいでしょう。
学校の授業は体系的に作られており、基礎から応用まで着実に知識を積み上げられるからです。
独学で未履修科目の受験も可能ですが、学校の授業とは別に膨大な学習時間の確保が必要になります。
普段履修している学校の授業や先生の有効活用が、現役合格への近道です。
得点につながりやすい科目を選ぶ

大学受験では、限られた時間のなかでいかに得点につなげられる科目を選択できるかどうかが重要です。
過去問を実際に解いてみることで、どの科目で安定して得点できるか事前に確認ができます。
例えば、暗記が得意なら地歴・公民、論理的思考が得意なら数学や物理がそれぞれ得点源になりやすいでしょう。
自分の学習スタイルや得意分野、性格を客観的に分析して、どの科目が得点につなげやすいかを見極めることが大切です。
短い期間で得点アップが期待できる科目を選ぶ
受験勉強に使える時間は限られているため、学習時間に対する得点の伸びやすさを考慮した科目選択が重要です。
例えば、暗記の比重が高い地歴・公民や理科基礎・古文などの科目は、勉強した分だけ点数が上がりやすい傾向があります。
「自分の学習スタイルや性格に合う科目が見つからない」「これ以上得点アップが期待できる科目がわからない」という方は、予備校に相談するのも一案です。
横浜予備校では、生徒一人ひとりの学力や性格、得意分野に合わせて科目選択をサポートしています。
プロ講師による徹底した学力分析に基づき、優先順位のつけ方や苦手分野へのアプローチなど具体的なステップを提示し、初めての受験でも不安なく勉強に取り組むことができます。
個人での計画の立て方に不安がある方は、ぜひ一度、横浜予備校の無料相談をご利用ください。
大学入学共通テストの教科と科目
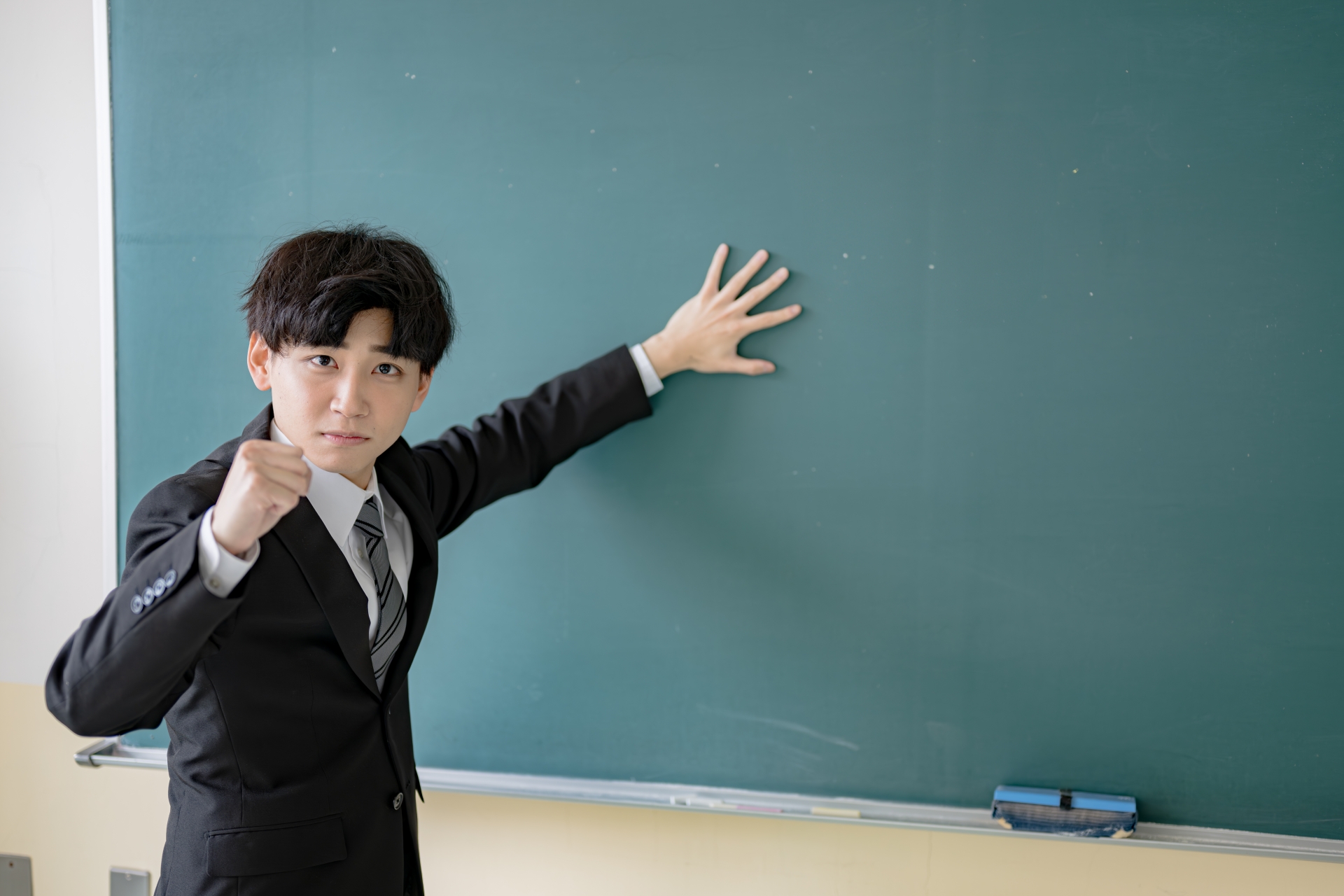
大学入学共通テストは、国公立大学では原則必須であり、多くの私立大学でも利用されている受験では避けて通れない関門です。
よって、適切な科目選択のためには共通テストの教科や科目を正しく理解しておく必要があります。
この章では、共通テストで受験すべき主要な5教科の概要と重要性を解説します。
自身の進路希望と照らし合わせながら、どの科目を選択する必要があるか確認していきましょう。
国語
大学共通テストの国語は、文系・理系を問わず、ほとんどの国公立大学で必須とされる教科です。
出題範囲は、近代以降の文章(論理文・文学文)と古典(古文・漢文)の課題文で、複数の大問から構成されています。
国語は読解力や論理的思考力を測る科目であり、学習の成果が表れるまでに時間がかかります。
受験直前から力を入れても手遅れになるリスクがあるため、高校の早い段階から基礎を着実に固めていくことが重要です。
数学
共通テストの数学は、数学I・数学Aと数学II・数学B・数学Cの2科目に分かれています。
数学は基礎からの積み重ねが重要であり、一度つまずくと遅れを取り戻すのが大変な科目です。
例えば、数学IIを学ばずに数学IIIを習得するのは困難なため、自分の志望する大学がどの範囲までを必要としているのかを早めに確認しておきましょう。
理科

理科の選択方法は複雑で、文系か理系かによって大きくパターンが分かれるため、注意が必要です。
基礎がつく科目群(物理基礎・化学基礎・地学基礎・生物基礎)と基礎がつかない科目群(物理・化学・地学・生物)から構成されています。
文系は基礎がつく科目群から2科目、理系は基礎がつかない科目群から2科目を選択しなければなりません。
理系学部では科目が指定されていることもあるため、志望大学の募集要項をあらかじめ確認してから判断しましょう。
地理歴史や公民
地理歴史と公民は、従来の日本史Aや世界史Bのような方式から選択パターンが変わりました。
地理は地理総合・地理探求があり、歴史は歴史総合・日本史探求・世界史探求から構成されるため、各科目の学習範囲の把握が重要です。
基本的に国公立大学の文系は2科目、理系は1科目を選択する傾向にあります。
受験科目と各科目の特性や学習量を照らし合わせて、自分に合った科目を選びましょう。
外国語
大学入学共通テストの外国語では以下の科目が選択できますが、特別な理由がない限りは英語を選択するのが一般的です。
・英語
・ドイツ語
・フランス語
・中国語
・韓国語
英語はリーディングとリスニングの合計点で評価され、大学によって配点比率が異なるため、志望校の比率を確認しながら対策を打つ必要があります。
英語以外の外国語は、筆記のみでさらに競争率が低いメリットがありますが、志望校の受験科目に含まれているかは事前の確認が大切です。
国公立大学と私立大学の受験科目

大学受験の科目選択は、国公立大学と私立大学のどちらに主眼を置くかで、学習計画が大きく変わります。
それぞれで求められる受験科目の数や種類が異なるため、両者の違いを正確に理解しておくことが必須です。
高校1年生や2年生の早い段階で志望校のことが意識できれば、無駄なく効率的に学習計画を立てられます。
この章では、国公立大学と私立大学の違いやそれぞれの受験科目の特徴を解説するため、今後の科目選択の参考にしてください。
国公立大学の受験科目
国公立大学の一般選抜は、大学入学共通テストと各大学の二次試験の結果で合否が決まります。そのため、国公立を目指す受験生は多くの科目の勉強が必要です。
共通テストでは原則として5教科7科目が課され、幅広い分野の知識を習得しなければなりません。
さらに二次試験では2~4教科の記述式試験が課されるため、国立大学の受験には総合的な学力が不可欠です。
私立大学の受験科目
私立大学の一般選抜は、3教科で受験する方式が主流で、文系と理系で大きく異なります。
文系は英語・国語・選択1科目、理系は英語・数学・理科のような組み合わせが一般的です。
国公立大学に比べて、学習の負担を特定の科目に集中させることができるのが特徴です。
得意科目を徹底的に伸ばして志望大学を目指す学習計画が立てやすいでしょう。
大学受験の科目選択の注意点

大学受験の科目選択では、良かれと思って下した判断がかえって自分の可能性を狭めてしまうこともあるため、注意が必要です。
安易に有利な科目を選んだり苦手科目を避けたりするのは、おすすめできません。
ここでは、多くの受験生が科目選択で見落としがちな3つの注意点を解説します。
注意点を頭に入れておくことで、後悔のない科目選択ができるようになるはずです。
早い段階で絞り過ぎないようにする
高校1年生や2年生の早い時期に、勉強する科目を極端に絞りすぎてしまうのは望ましくありません。
高校生活のなかで教師や友人、環境の影響で興味が変わり、志望校を変更する可能性が十分にあるからです。
特に志望校が固まっていない段階では、なるべく幅広い科目を履修し、基礎学力を維持しておきましょう。
満遍なく多くの分野を学習しておくことで、3年生になったとき科目の選択肢を広げることができます。
得点調整が入るケースも考慮する
大学入学共通テストの選択科目間では、問題の難易度によって得点調整が行われる場合があります。
これは特定の科目がほかの科目と比較して著しく平均点が低い場合に、公平性を保つために実施される措置です。
難易度にふり回されずに得点を狙うには、得点調整に頼らず、自分が高得点をとれる科目を選択する必要があります。
過去数年間の平均点の推移や出題傾向を調べたり実際に過去問を解いたりして、難易度が安定している科目を選びましょう。
得意科目や苦手科目にとらわれ過ぎない

受験科目を選択する際に、得意科目を選び、苦手科目を避けるという感覚を基準にするのはおすすめできません。
得意と思う感覚がテストでの得点力と一致するとは限らず、苦手科目も学習の仕方によっては大きく伸ばせる可能性があります。
大学受験の科目選択は現時点での好き嫌いで判断するのではなく、配点や問題との相性、学習の伸びしろなど多くの視点から総合的に判断しましょう。
自分一人での判断が難しい場合は、専門家のアドバイスを求めることが有効です。
横浜予備校では、経験豊富な講師陣が生徒一人ひとりの学力だけでなく、性格や目標まで深く把握したうえで、適切な科目選択や進路のアドバイスを行っています。
特に、1対1〜4人までの少人数制による徹底した個別指導を通じて、生徒の特性に合った学習環境と進路戦略を提供しています。
大人数の授業では見落とされがちな細かな課題にも、担当講師が丁寧に対応するため、不安やつまずきを早期に解消できます。
進路に迷っている方や、後悔のない選択をしたい方は、まずは無料相談で今の状況をお聞かせください。志望校合格に向けた一歩を、一緒に踏み出しましょう。
大学受験の科目選択で失敗しないために

この記事では、大学受験の科目選択で失敗しないためのコツ、大学入学共通テストの仕組みや注意点を解説してきました。
ここまで解説してきたように、受験に必要な教科や科目が多岐にわたり、生徒や保護者だけで完璧な戦略を立てるのは簡単ではありません。
大学受験の科目選択は、合否を左右する初めの分岐点です。科目選択での失敗を未然に防ぐには、早期から進路指導の専門家や信頼できる予備校のサポートを得ることが極めて有効です。
横浜予備校では、医学部や難関大学に特化した指導実績を活かし、蓄積された出題傾向や合格データをもとに、精度の高い進路指導を行っています。
経験豊富な講師陣が個別に指導を行うことで、苦手科目を得意科目へと転換し、得点力を着実に伸ばすことが可能です。
大学受験の科目選びに迷っている方や、学習の進め方に不安がある方は、ぜひ無料の学習相談をご利用ください。
資料請求も受け付けておりますので、まずは一歩を踏み出してみませんか。横浜予備校が、あなたの合格までを全力でサポートします。












