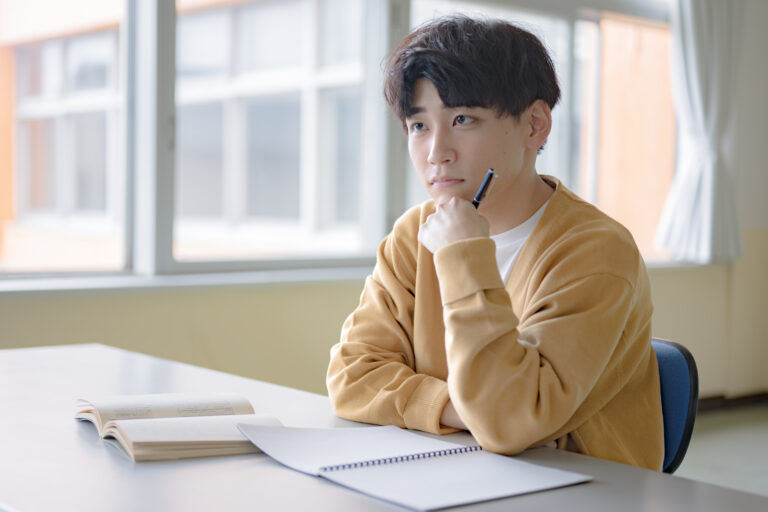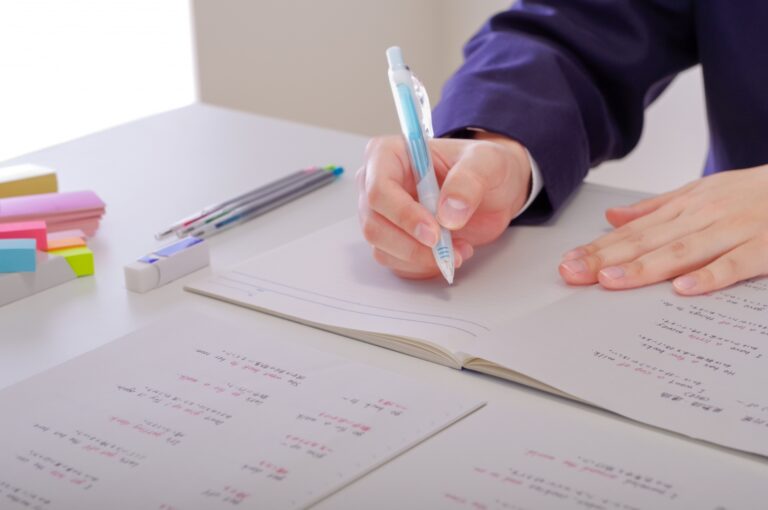
大学入学共通テストのボーダーラインを見て、不安を感じる受験生も多いのではないでしょうか。
医学部や難関大学を志望する人にとって、ボーダーラインを正しく理解することは受験戦略を立てるうえでとても重要です。
ボーダーラインとは、合格得点の目安であり、合格率50%の得点ラインを指します。
ボーダーラインを正しく理解し、それに基づいて戦略的に勉強を進めれば、逆転合格も可能です。
模擬試験の結果に一喜一憂せず、合格の可能性を上げるために今できることを考えていきましょう。
この記事では、共通テストのボーダーラインとは何か、ボーダーラインの算出方法を解説します。
また、大学別の得点率目安や結果の受け止め方についても説明します。
しっかりと理解し、共通テストに向けて今からやるべき対策を実行しましょう。
目次
共通テストのボーダーラインの意味と計測方法

共通テストのボーダーラインは、志望校合格の可能性を測るための重要な指標です。
ここでは、ボーダーラインの意味と計測方法について紹介します。
共通テストのボーダーラインの意味
共通テストのボーダーラインとは、各予備校が算出した合格の確率が50%の得点ラインのことです。
これは、予備校が過去の受験者データをもとに独自に算出した目安の値です。
予備校によって差はありますが、一般的には次のように合格率が分けられます。
・A判定:合格可能性80%以上
・B判定:合格可能性65%
・C判定:合格可能性50%
・D判定:合格可能性35%
・E判定:合格可能性20%以下
ボーダーラインは常に意識すべきですが、あくまで合格可能性を示す目安であり、実際の合否とは異なる場合があることに注意しましょう。
ボーダーラインの計測方法
ボーダーラインの計測方法は、予備校が過去の受験データや模試結果をもとに算出しています。
ボーダーラインの計測に影響を与える要因は以下の5つです。
・受験者数の増減:受験者数が増えれば競争が激化し、その結果としてボーダーラインが上昇する傾向があります。
・問題の難易度:問題が難化すると全体の得点が下がりやすくなるため、ボーダーラインも下がります。逆に、問題が易化した年は高得点を取る受験生が増え、ボーダーラインが上昇します。
・志望動向の変化:ある職種の人気が高まると、それに関連した学部・学科への志望が集中し、その学部のボーダーラインが上昇することがあります。
・入試方式の変更:募集定員の増減や選抜方式の変更により、共通テストの重みが増す場合はボーダーラインが高くなります。
・二次試験の配点や難易度:共通テストの配点が高い大学では、共通テストの得点が合否に直結するため、ボーダーラインも高くなります。
ボーダーラインは受験環境の変化や制度の影響を強く受ける不安定な指標であることを理解しておくことが重要です。
そして、ボーダーラインを鵜呑みにせず、複数年の傾向や大学ごとの事情を踏まえた上で柔軟に判断することが大切です。
予備校ではボーダーラインの情報を活用し、冷静かつ戦略的に自分の位置を見極めることができます。
横浜予備校では、共通テストの得点やボーダー判定をもとに、一人ひとりに合わせた具体的な学習戦略をプロ講師と専属コーチが個別に提案します。
過去の傾向や出題傾向を踏まえた実践的な対策を通じて、逆転合格も視野に入れたサポートを行っています。
さらに、オリジナル教材や学力診断で、共通テスト後の「今やるべきこと」を明確にし、時間を無駄にせず合格力を高めていけるのが横浜予備校の強みです。
「共通テストのボーダーに届いていない」「志望校を変えるべきか悩んでいる」という方は、ぜひ一度、横浜予備校の無料相談をご利用ください。
大学別過去の共通テストボーダーライン目安

ここでは、大学別の共通テストボーダーラインをまとめました。志望している大学のボーダーラインを参考にして、学習計画を立てましょう。
東大・京大
東京大学や京都大学を目指す場合、共通テストでの得点率は85〜90%が目安となります。
これらの大学では二次試験が重視されますが、共通テストの得点が一定基準に満たない場合には、そもそも二次試験に進めない足切りが実施されることが多いため注意が必要です。
共通テストでは確実に足切りラインを超えたうえで、二次試験対策に力を注ぐ必要があります。
早稲田・上智
私立最難関の早稲田大学や上智大学では、共通テスト利用入試におけるボーダーラインは78〜96%でとても高水準です。
特に共通テスト利用方式は募集人員が少なく、倍率が高いため、ほんの数点の差が合否を左右することもあります。
共通テストの結果がそのまま合否に直結するため、一般選抜よりも一層の正確さと高得点が求められます。
MARCH
MMARCH(明治・青山学院・立教・中央・法政)の共通テスト利用方式のボーダーラインは、大学や学部によって差があるものの、概ね78〜88%が目安とされています。
このゾーンでは、共通テストの配点比率が高めに設定されているケースも多く、得点率がそのまま合否に反映されやすい傾向にあります。
日東駒専
日東駒専(日本大学・東洋大学・駒澤大学・専修大学)の共通テスト利用方式のボーダーラインは、おおむね65〜75%が目安とされています。
比較的手が届きやすい水準に見えますが、学部や年度によっては上昇傾向にあるため、油断は禁物です。
前述した通り、ボーダーラインはあくまで自分の立ち位置と志望校との距離を測る目安であり、伸びしろを考慮していません。
今後足りない部分を埋めていけば、逆転合格も十分に可能です。
諦めずに勉強に励みましょう。
共通テストボーダーラインの判定のとらえ方

模擬試験やテストでは受験後の次の行動が大切です。
C判定やD判定が出た場合でも、次の行動次第で判定を覆すことができます。
本番までの残り時間を考慮し、模擬試験の結果に一喜一憂せず、自分の学習に集中しましょう。
ここでは、各判定を取った際の捉え方を紹介します。
A判定の場合
合格の可能性は80%以上でとても高い水準ですが、油断は禁物です。本番では予想外の出題傾向の変化やケアレスミスが起こることもあり、また予備校の判定には一定の誤差があるため、A判定=合格確定ではありません。
最後まで気を抜かず、これまでの学習を土台に、記述対策や過去問演習など二次試験に向けた対策を徹底しておきましょう。
B判定の場合
B判定は、合格可能性が65%以上と比較的高い水準にありますが、まだ安心できる状態ではありません。現状に満足せず、なぜA判定に届かなかったのか、その理由を冷静に分析することが重要です。
弱点分野の洗い出しや、時間配分・ミスの傾向を見直すことで、得点力の底上げが期待できます。
C判定の場合
C判定はボーダーライン上であり、十分に合格圏内と捉えて問題ありません。
あと一歩の努力で志望校に届く位置にいるため、ここからの対策が結果を大きく左右します。
まずは「なぜB判定に届かなかったのか」「この問題が解けていれば結果はどう変わったか」など、模試結果をもとに現状を冷静に分析しましょう。
D判定の場合
D判定と聞くと不安になるかもしれませんが、実際には受験生の6割がE判定で志望校を受験しているというデータもあります。
つまり、D判定からの逆転合格は決して珍しいことではありません。
大切なのは、なぜD判定だったのかを正確に分析することです。例えば、苦手分野の配点が高かった、ケアレスミスが重なったといった明確な要因がある場合、対策の優先順位も立てやすくなります。
E判定の場合
E判定が出たとしても、それはあくまで現時点での状況にすぎず、合否を決定づけるものではありません。
模擬試験はその時点での学力を測る指標であり、今後の努力次第で状況はいくらでも変えられます。
特に共通テストは、対策が明確で取り組みやすく、短期間でも得点が伸びやすい科目です。
志望校合格に向けて、過去問や予想問題、苦手分野の克服など、さまざまなシミュレーションをしながら戦略的に勉強を進めていきましょう。
共通テストのボーダーラインを知ったときの気持ちの持ち方

ここでは、共通テストのボーダーラインを知ったときにどう気持ちを保つべきかについて解説します。
結果に一喜一憂せず前を向いて勉強を続けるためには、以下の3点を意識することが大切です。
・ボーダーラインは目安にすぎない
・結果に一喜一憂せず次の試験に向けた勉強をする
・周りの受験生の判定を気にしない
それぞれ詳しく解説していきます。
ボーダーラインは目安にすぎない
ボーダーラインはあくまで目安であり、過信するのは危険です。
ボーダーラインは前年のデータを参考にして算出されているため、今年の状況が変化する可能性があります。
また、共通テストでボーダーを下回っていても、二次試験で挽回して合格する受験生は多くいます。
特に、二次試験の配点が高く設定されている大学では、共通テストの得点を逆転することが可能です。
志望校を早期に決定し、過去問対策などをしっかりと積み重ねてきた方にとって、共通テストの点数だけで志望校を諦めるのはもったいないことです。
受験校の決定は、学習状況や今後の戦略を含めて総合的に判断することが大切になります。
結果に一喜一憂せず次の試験に向けた勉強をする
数字に一喜一憂しないことが、受験においてとても大切です。
模擬試験の結果やボーダーラインは不安定な指標であり、問題の難易度や得意不得意によって変動します。
毎回のテスト結果に一喜一憂せず、冷静に数字を分析して次の模擬試験や入試に備えましょう。
テストのたびに落ち込んでいる時間はありません。
残り時間を有効に使い、次の行動を取ることが重要です。
周りの受験生の判定を気にしない
周囲の判定を気にしないことで、気持ちの切り替えが楽にできます。
大切なのは、今の自分に何が必要かを見極めることです。志望校や選択科目、勉強の進み具合、得意不得意など、状況は一人ひとり異なります。
合否を決めるのは、今後の学習と試験当日のパフォーマンスです。
周りに惑わされて焦っても実力は伸びません。
周囲の判定を気にして時間を浪費するよりも、自分の成長に集中することが、合格への近道です。
横浜予備校では、共通テスト後の学力分析から二次試験対策まで、一人ひとりに適切な戦略を立てる個別指導を徹底しています。
模試の結果やボーダーに一喜一憂するのではなく、今の自分に何が必要かを明確にし、合格に向けた近道を提示するのが私たちの強みです。
さらに、専用の学習スペースやオリジナル教材によって、限られた時間を最大限に活用できる環境を整えています。
「今からでも間に合うのか」「志望校は変えるべきか」といった悩みも、まずは横浜予備校の無料相談でご相談ください。
共通テストのボーダーラインを鵜呑みにせず勉強を続けることが大切

共通テストのボーダーラインを鵜呑みにせず、勉強を続けることが大切です。
ボーダーラインは自分を分析するための指標であり、受験の結果を示すものではありません。
どのような判定が出ても、結果に振り回されず自分の課題と向き合うことが合格への近道です。
判定結果は、どれくらい点数を取れば逆転できるかを考えるための材料にもなります。
不安がある場合は、学習計画やメンタル面のサポートをしてくれる予備校を活用するのもおすすめです。
横浜予備校では、大手予備校での指導経験があるプロ講師が、共通テストの出題傾向とボーダーラインを踏まえた戦略的な学習プランを個別に作成します。
現状の得点力から志望校合格までに必要なステップを明確にし、合格への道筋を示します。
さらに、集中できる自習環境や24時間対応のLINEといったサポート体制も整っているため、最後まで安心感を持って学習に取り組むことが可能です。
「あと何点必要なのか」「どうすればボーダーを超えられるのか」に悩んでいる方は、まずは横浜予備校の無料相談を活用してみてください。
合格への現実的な道筋を、共に描いていきましょう。