
大学受験が近づくと、勉強に集中できなかったり、気分が沈みやすくなったりすることがあります。
こうした変化は、受験期特有のストレスや緊張によって引き起こされる受験うつのサインかもしれません。
本記事では、大学受験を控えた受験生や保護者の方に向けて、受験うつの原因や症状、予防法についてわかりやすく解説します。
ご自身やお子さまの状態を確認する手がかりとして、ぜひお役立てください。
目次
大学受験でメンタルを病む受験うつとは

大学受験の時期は、学力だけでなく心の状態も大きく関わります。
強い不安や緊張が長く続くと、心のバランスを崩すきっかけになります。
その結果、モチベーションが上がらなかったり、眠れなくなったりといった不調が現れることがあります。
これらの状態を、受験うつと呼ぶことがあります。
受験うつは正式な病名ではなく、受験に関連した心と体の不調をまとめて表す言葉です。
気分が沈んだり、授業に集中できなかったり、体が重く感じるといった症状が続く場合には注意が必要です。
受験うつは、誰にでも起こる可能性があります。
本人だけでなく、まわりの大人が変化に気付くことも大切です。
気分が沈んでいるようであれば、早めに休息を取るか、信頼できる大人に相談しましょう。
受験うつの主な原因

受験うつは、単に気分が落ち込むという一時的なものではありません。
ほとんどの場合、いくつものストレス要因が複雑に絡み合って心の不調を引き起こします。
自分では気付かないうちに心が疲れてしまうケースも多く見られます。
・受験勉強が思うように進まないストレス
・周囲からのプレッシャー
・ライバルとの競争
次の項目では、それぞれの原因について詳しく見ていきましょう。
受験勉強が思うように進まないストレス
計画通りに学習が進まなかったり、模試の結果が思わしくなかったりすると、気持ちの面で不安定になりやすくなります。
頑張っているのに成果が見えないと、強いストレスを感じやすいです。
特に真面目な性格の人は、結果が出ない状況を必要以上に深刻に受け止めやすく、落ち込みが長引く傾向があります。
その状態が続くと、モチベーションが低下したり、集中しづらくなったりといった変化が見られます。
まずは、誰にでも思い通りにいかない時期があると受け止め、自分を責めすぎない姿勢が大切です。
周囲からのプレッシャー
家族や先生、塾の講師からの期待を強く感じると、それが重荷になってしまうことがあります。
期待に応えたい気持ちが強いほど、思うように成果が出なかったときに自分を責めやすくなります。
また、親の前で弱音を吐きづらい環境だと、心の負担を一人で抱え込みやすいです。
特に、周囲からプレッシャーになるような言動があると、逃げ場のない状況に追い込まれたように感じることもあります。
まずは、自分の気持ちや悩みを話せる相手を見つけることが、心の負担を軽くする第一歩です。
ライバルとの競争

ライバルとの競争が精神的な負担につながるケースは多く見られます。
志望校が同じ友人の模試結果を聞いたり、SNSなどで同級生が長時間勉強している様子を見かけると、焦る気持ちが強くなることがあります。
自分も同じように頑張らなければという思いがプレッシャーになることも少なくありません。
また、他人と比較することで、自分の努力を正しく評価できなくなりがちです。
本当はしっかりと取り組んでいても、周囲と比べてしまうと足りないと感じてしまい、落ち込む原因になります。
自分に合ったペースを大切にし、他人との違いを受け入れながら進む姿勢が重要です。
横浜予備校は、医学部や難関大に特化した徹底サポートが強みの予備校です。
1〜4人の極少人数制授業によって、講師が一人ひとりの様子や悩みにも目を配れる体制を整えています。
さらに、週1回の面談や24時間LINE相談など、生徒と保護者双方に寄り添ったサポートが特徴です。
また、使用する教材は入試に特化したオリジナルテキストを採用しており、限られた時間でも成果を出せるよう設計されています。
勉強の悩みだけでなく、メンタル面も一緒に支えることで、最後まで前向きに走り抜けられる環境がここにあります。
「大学受験がつらい」「病みそう」と感じている方は、まずは無料相談でお気軽にご相談ください。
受験うつの主な精神症状や身体症状
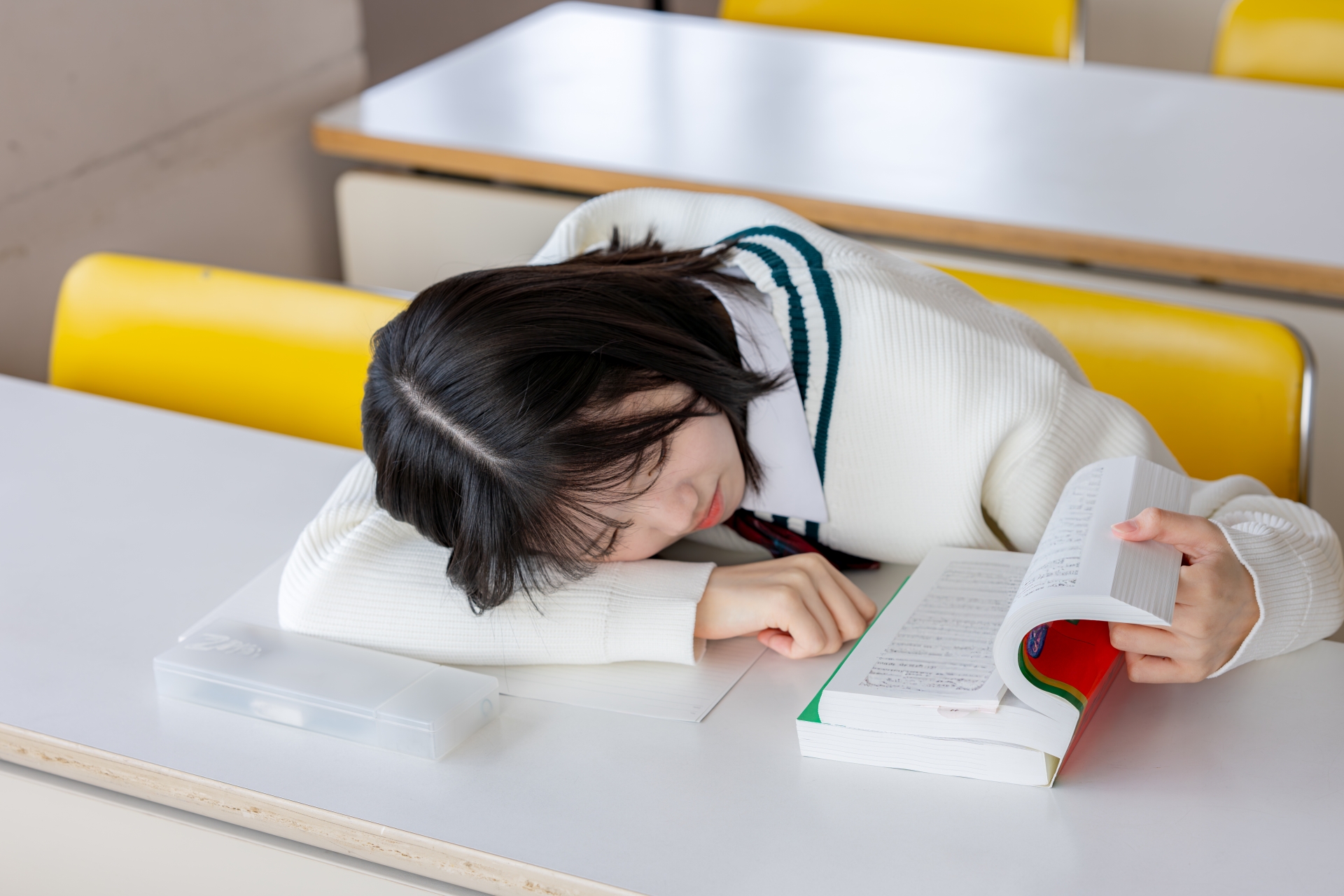
受験うつの症状は、精神面と身体面の両方にあらわれます。
主な症状には以下のようなものがあります。
・精神症状:勉強に集中ができなくなる
・精神症状:イライラしやすい
・精神症状:不安や緊張感が大きくなる
・精神症状:意欲を失い学校を休みがちになる
・身体症状:食欲不振や吐き気がある
・身体症状:夜眠れず日中に眠気がある
・身体症状:疲労感や倦怠感がある
・身体症状:頭痛がする
次の項目では、それぞれの症状について詳しく見ていきましょう。
精神症状:勉強に集中ができなくなる
受験うつの初期に感じる違和感が、集中力の低下です。
机に向かっていても頭に内容が入らない、何度も同じところを読み返してしまうといった状態が続くと、学習の効率が下がっていきます。
このような集中力の乱れは、単なる疲れや気の緩みではなく、心の不調が関係している場合があります。
そのため、集中できない状態が数日以上続くようであれば、早めに心身のコンディションを整える工夫が必要です。
十分な睡眠や適度な休息を取り入れることが、状態の改善につながることもあります。
精神症状:イライラしやすい
受験期に心のバランスを崩し始めると、ささいなことで怒りっぽくなることがあります。
普段なら気にならないことに反応したり、家族や友人に対してきつい口調になったりする場面が増えることもあるでしょう。
これは、心の疲れやストレスがたまり、感情をうまくコントロールできなくなっている状態です。
感情が不安定なときは、一人で抱え込まず、気持ちを言葉にして整理する時間を持つことが大切です。
精神症状:不安や緊張感が大きくなる

受験が近づくと、このままで合格できるのかと不安になる気持ちが強くなり、過度な不安や緊張に悩まされることがあります。
緊張から夜眠れなくなったり、頭のなかで失敗のイメージばかりが浮かんだりすることもあるでしょう。
特に、不安や緊張によって食事が喉を通らなくなったり、授業や模試で実力が出せなくなったりする場合は、心のケアが必要です。
リラックスできる音楽を聴いたり、体を軽く動かしたりすることで、少しずつ気持ちが落ち着くことがあります。
精神症状:意欲を失い学校を休みがちになる
受験に向けて努力を続けていても、心の疲れが蓄積すると、勉強への意欲が低下してしまうことがあります。
朝起きるのがつらくなったり、授業に参加する気力が湧かなくなったりすることは、心身が限界を迎えているサインかもしれません。
このようなときは、無理をせず、一度立ち止まることも大切です。
信頼できる大人やカウンセラーと話すことで、気持ちの整理がつき、少しずつ回復に向かうことがあります。
身体症状:食欲不振や吐き気がある
受験のストレスが強まると、胃腸の働きが乱れ、食事が喉を通らなくなり吐き気を感じることが増えてきます。
特に、普段は食欲があっても急に食べられなくなったり、好物すら食べられなくなるといった変化があった場合には注意が必要です。
体力の低下だけでなく、思考力や集中力にも影響が出てしまう可能性があります。
食事をとることが負担に感じられるときは、無理に量を食べようとせず、消化のよい食品や温かいスープなどを少しずつ取り入れるとよいでしょう。
身体症状:夜眠れず日中に眠気がある

受験に対する不安や緊張は、睡眠の質やリズムにも影響します。
睡眠不足が続くと、脳や体の疲れがとれず、日中に強い眠気やだるさを感じやすくなります。
その結果、授業に集中できなくなったり、勉強の効率が下がってしまうこともあるため、早めの対処が大切です。
就寝前はスマートフォンの使用を控え、ぬるめの入浴や深呼吸などで気持ちを落ち着かせましょう。
また、生活リズムが大きく乱れていると感じた場合は、カウンセラーや医師に相談してみるのも選択肢の一つです。
身体症状:疲労感や倦怠感がある
十分に寝たはずなのに体が重い、気力が湧かないなどの疲労感や倦怠感は、見過ごされがちな受験うつのサインです。
こうした体調不良は、単なる疲れとは異なり、気分の落ち込みや無力感とあわせて表れることがあります。
特に、いつも通りの生活が難しくなったり、好きだったことに興味が持てなくなった場合は注意が必要です。
生活リズムや栄養バランスを見直し、無理をしすぎないように心がけることが第一歩です。
少しでも違和感を感じたら、周りに相談するようにしましょう。
身体症状:頭痛がする
受験期のストレスが原因で慢性的な頭痛に悩まされる受験生も少なくありません。
緊張状態が長く続くと、肩や首の筋肉がこわばり、血流が悪くなることがあり、これが頭痛につながります。
加えて、睡眠不足や栄養の偏りも、体調を崩す一因となりやすいため注意が必要です。
頭痛が頻繁に起こる場合は、体からの重要なサインと受け止めましょう。
受験うつの治療方法や予防法

受験うつを改善するためには、早めに適切な対応を取ることが重要です。
ここからは、現在の状態を立て直すための治療方法と、日々の生活のなかで心の不調を未然に防ぐ予防法について紹介します。
治療方法
受験うつが疑われる場合は、まず心療内科やメンタルクリニックなどの医療機関を受診することが大切です。
状態に応じて、カウンセリングや投薬などの治療を受けることがあります。
カウンセリングでは、不安やプレッシャーの背景を整理し、思考の偏りを少しずつ緩めていきます。
また、必要に応じて医師が抗うつ薬や抗不安薬などを処方する場合もあります。
ただし、薬に頼ることが目的ではなく、生活を整えるための一時的な手段として考えることが大切です。
まずは無理せず、心の専門家に相談してみましょう。
予防方法
受験うつを防ぐためには、心と体のバランスを保つ生活を意識することが重要です。
まずは、生活リズムを安定させることが基本となります。
起床と就寝の時間を一定に保ち、睡眠時間をしっかりとるようにしましょう。
さらに、勉強においては完璧を求めすぎないこともポイントです。
自分の得意と不得意を把握し、できることから取り組むようにすると心の負担が軽くなります。
受験のことを一人で抱え込まず、信頼できる人に相談する習慣を持つことも効果的です。
横浜予備校では、医学部や難関大学を目指す生徒を対象に、少人数制(1クラス平均2名)での徹底サポートを実施しています。
学習計画の立案や定期的な面談により、一人で抱え込まずに着実に前進できる仕組みが整っています。
さらに、保護者との連携を大切にし、24時間LINE相談サービスなど家庭とのコミュニケーション体制も充実していることが特徴です。
メンタルケアにも配慮した学習環境だからこそ、勉強の不安や悩みに寄り添いながら学力を伸ばすことが可能です。
「勉強のことで心が疲れてきた」「このまま一人で頑張れるか不安」という方は、まずはお気軽にご相談ください。
大学受験でメンタルを病む前に

受験勉強は、将来を左右する大切な時期である一方で、精神的な負担も大きくなりがちです。
そのため、早い段階から心のケアを意識することが重要です。
日々の小さな不調にも気付き、無理をしすぎない姿勢を持つことで、受験うつの予防につながります。
また、一人で抱え込まず、身近な人や専門家に相談することも大切です。
不安な気持ちや悩みは、言葉にして初めて軽くなることがあります。
受験の不安は、学習環境や適切なサポートを受けることで大きく軽減できます。
心の健康も学力と同じように大切にし、受験に臨める環境を整えていきましょう。
横浜予備校では、生徒一人ひとりに寄り添った個別指導と徹底した面談サポートを通じて、学力面だけでなく精神面のケアにも力を入れています。
1対1〜最大4人の極少人数制だからこそ、悩みや不安に気づきやすく、早期のフォローが可能です。
さらに、24時間対応のLINE相談窓口を保護者・生徒向けに設置し、「勉強がつらい」「やる気が出ない」といったメンタルの悩みもいつでも相談可能。
定期的な面談や、必要に応じてカリキュラムの見直しも行い、無理のない学習環境を整備しています。
「大学受験で病みそう」「勉強が思うように進まず苦しい」と感じている方は、まずはお気軽にご相談ください。
受験のプロ講師陣と充実したサポート体制が、あなたに合った学習プランをご提案します。











