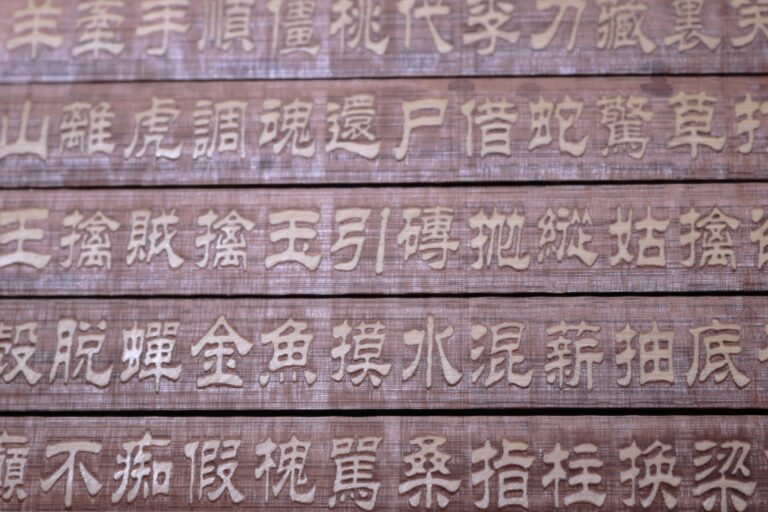
共通テストは、国公立大学合格のためには避けては通れない試験です。そのなかの漢文は、全体として配点は低いものの、しっかり点数をとる必要があります。医学部のような難関大学を受験する場合、小さな差が合否を分けるため、合格のためには満点をとっておきたい科目です。
読者のなかには、漢文の対策を後回しにしてしまい、直前になって満点をとれるか不安になっている方もいるでしょう。しかし、漢文は短期間でも効率よく学習すれば高得点が狙えます。この記事では、漢文の勉強法・参考書・解き方について、具体的に解説します。漢文を効率的に学習して満点を目指しましょう。
目次
共通テスト漢文の試験概要

漢文の出題形式は、漢字問題・書き下し文・読解問題があります。
しかし、漢文の試験内容に関しては曖昧で、どの分野が出題されるのか具体的にわかっていない方もいるでしょう。
この章では、漢文の出題形式と範囲、問題の傾向を説明します。
漢字問題
共通テスト漢文には、漢字の意味を問う問題が1問目で3つ出題されます。
漢文は現代語でも使われている漢字が多く、理解しやすい科目です。
しかし、読み慣れている漢字でも異なる意味で問われることがあるため、漢字の知識が重要です。
そのため、漢字の読みや意味を学習する必要があります。
漢字一文字では意味をイメージしにくくても、熟語から連想すると理解しやすくなります。
文脈がわかれば単語を覚えていなくても解ける場合がありますが、しっかり学習すれば理解を深めることが可能です。
書き下し文
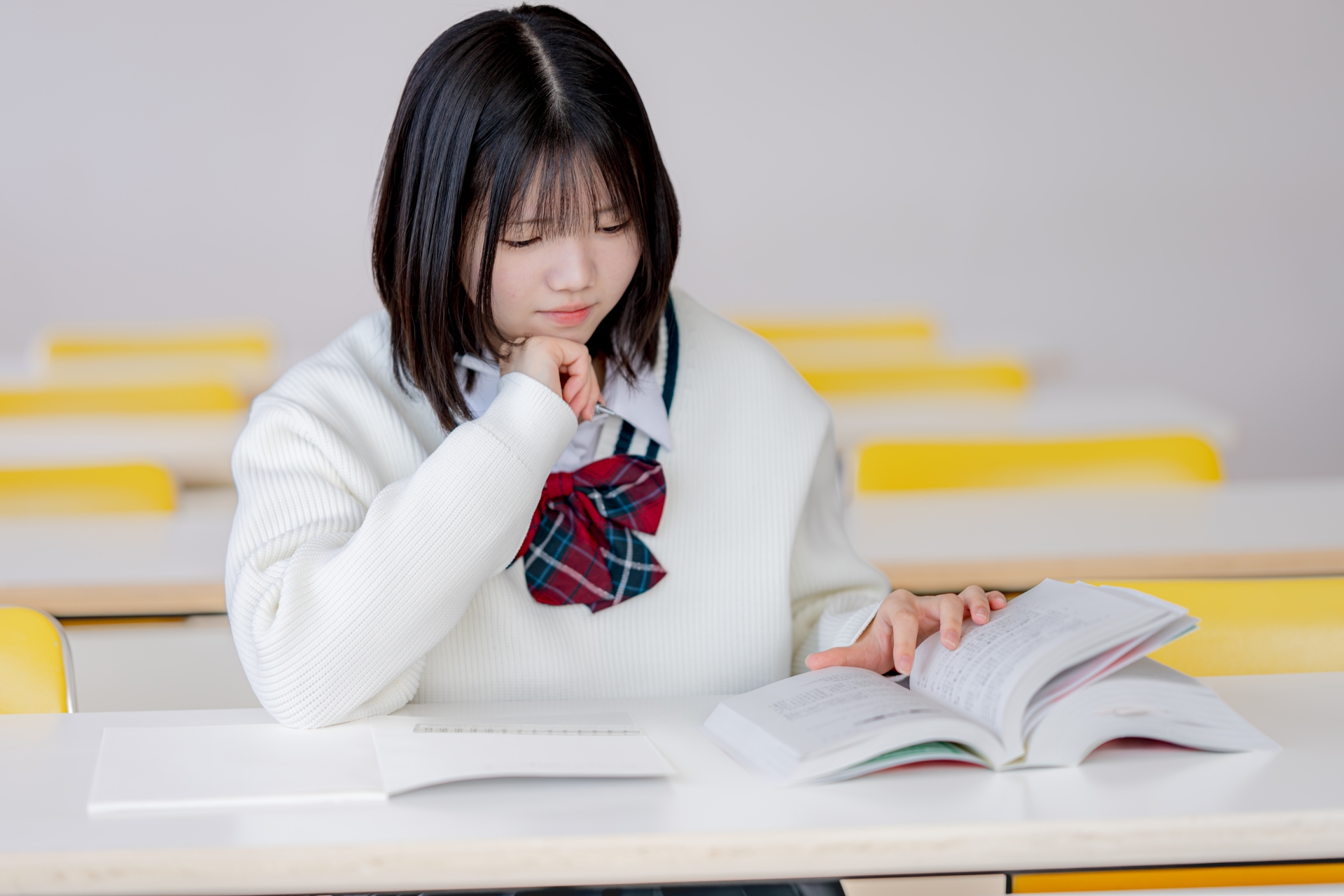
書き下し文とは、日本人が漢文を読みやすいように訓点をつけたものであり、訓点は返り点や送り仮名などのことです。
漢文では2問目で書き下し文と和訳が出題されます。
書き下し文において、句法の学習は不可欠です。
句法は漢文を正しく読むためには必要な知識であり、句法の活用方法を理解していないと、読解につながりません。
書き下し文の問題では、句法の知識を使って不自然な選択肢を排除して、明確な根拠で問題を解くと正解率を上げることができます。
使役や受身、否定など多用される句形は、しっかり理解しておきましょう。
書き下しができるようになれば、文章の意味を深く理解できるようになり、問題も解きやすくなります。
読解問題
漢文の3問目以降は読解になり、共通テスト漢文の7割ほどを占めます。
本文の内容を理解しているかが問われる部分です。
解答の根拠は問題となった箇所の近くにあるため、傍線部の付近に注目することがポイントです。
読解問題を解くには、句法を理解している必要があります。
句法を活用できれば、著者の意図や物語の主題をしっかり把握できます。
共通テスト漢文の勉強法

共通テストの漢文が大事な科目であることはわかるけれど、どう勉強すればよいか迷っている方がいるかもしれません。
漢文は、返り点や句法・重要語句を覚えることが大切です。
また、現代文や古文の基礎力も活かせます。
この章では、共通テスト漢文の勉強法を具体的に解説します。
現代文・古文の勉強をする
漢文を理解して高得点を目指すには、現代文や古文の勉強も欠かせません。
私立大学や国公立大学の2次試験では、古文と漢文の融合問題が出題されることもあります。
私立大学や国公立大学の2次試験では、古文と漢文の融合問題が出題されることもあります。
漢文の書き下し文は歴史的仮名遣いを用いて書かれるため、古文のような形態になります。
そのため古文の文法や読み方が理解できていないと、漢文の意味をしっかり理解することは困難です。
また、古文を現代文に訳せないと理解が不十分になるだけでなく、現代文の読解ができないと古文や漢文も十分に読み解けないことになります。
しかし、学習する時間は限られています。
重要なことは的確に理解できるよう文法をしっかり把握すること、文の内容や文化的な背景を理解すること、過去問の傾向を知ることです。
過去問については後述します。
返り点・句法・重要語句を覚える

漢文の理解には、返り点・句法・重要語句を覚えることが必要です。
一つひとつの読み方や意味がわかっていないと、漢文は正確に読めません。
文章を読み解くだけでなく、句法を理解していれば効率的に選択肢を絞り込むことも可能です。
レ点や上中下点などの返り点、否定形や反語形などの句法を書き下し文と合わせて覚えることで、理解を深められます。
重要語句を学習する方法の一つが、単語帳を購入して覚える方法です。
よく見る語句を自分でまとめることもよい方法です。
わからない語句に推測した意味を書き入れ、間違っていた語句をノートにまとめて暗記すると理解が進みます。
また、漢文を学習するときは黙読だけでなく音読すると、知識の定着が早まります。
過去問で問題演習を積む
漢文の学習には、過去問で問題演習を積むことも重要です。
過去問を行うと問題の傾向がわかるだけでなく、自分の苦手な部分が浮き彫りになり、学習の効率が上がります。
過去問を使用するタイミングは、学習計画を立てると把握しやすくなります。
学習計画は限られた時間のなかで何を優先するべきか、どのように勉強していくかを明確にするものです。
試験日から逆算し、基礎の学習から過去問と復習をする日を設定すれば、効率よく勉強できます。
過去問は良問が多く見られるだけでなく、前述したとおり、問題の傾向を把握するために必要な教材です。
繰り返し解くことで、苦手な項目の復習や試験の予行練習にもなるため、おすすめの勉強方法です。
漢文を学習するにあたって、方法はわかったけれどなかなか自分一人で取り組むのは難しい、と感じる方もいるかもしれません。
基礎から読解まで限られた時間でどのように学習すればよいか、学習計画をどうやって立てればよいか、悩む方もいるでしょう。
私たち横浜予備校は、特に医学部や難関大学に強い塾として定評があります。
少人数制や個人指導を徹底しており、生徒一人ひとりの学力や目標に合わせたサポートが可能です。
また、生徒個人の自習スペースがあるため、集中して学習できる環境が整っています。
各生徒の学力を分析し、それぞれに適したカリキュラムを作成するため、志望校に合わせた学習ができます。個人的なカリキュラムに基づいた学習方法を提案できることが、横浜予備校の特徴です。
自習だけでは学習に限界を感じている方、効率的に学習を進められる方法や学習計画を立てたい方は、横浜予備校にまずはご相談ください。
生徒一人ひとりに合わせたプランをご提案します。
共通テスト漢文の参考書を選ぶポイント

漢文の学習を進める際には、参考書を活用すると効率的に学習できます。
しかし、種類が多すぎてどれを使えばよいか迷っている方もいるでしょう。
ポイントを押さえれば、使いやすい参考書を探すことが可能です。
この章では、自分に合う参考書を選ぶポイントを解説します。
自分のレベルに合ったものを選ぶ
共通テスト漢文の参考書は、自分のレベルにあったものを選ばなくてはいけません。
レベルに合ってないと、問題を解きにくかったり解答を見ても理解できなかったりするため、学習が進みにくい場合があります。
参考書はレベル別に 見ると、初心者向け・中級者向け・上級者向けのものがあります。
初心者向けは句法や単語を効率的に学習できるもの、中級者向けは漢文読解の基礎を固めるもの、上級者向けは論理的な思考力で解答できるように練習するものです。
効率的に学習するために、自分のレベルを把握して参考書を選びましょう。
アウトプットとインプットを同時にできるものを選ぶ
アウトプットとインプットを同時に行えるのも、参考書を選ぶときのポイントです。
時間が確保できるならば、それぞれに特化した参考書を準備するのもよいかもしれません。
しかし、漢文以外に学習しなければならない科目は多く、漢文のみに時間をかけられない方もいるでしょう。
漢文の知識を理解するインプットと、知識を活用して問題を解答するアウトプット、両方一冊で実施できる参考書の方が効率的に学習できます。
インプットだけでは知識を定着させることは困難です。
インプットとアウトプットを同時に行えれば、理解を深められるだけでなく、復習もしやすくなります。
問題集は解説が詳しいものを選ぶ
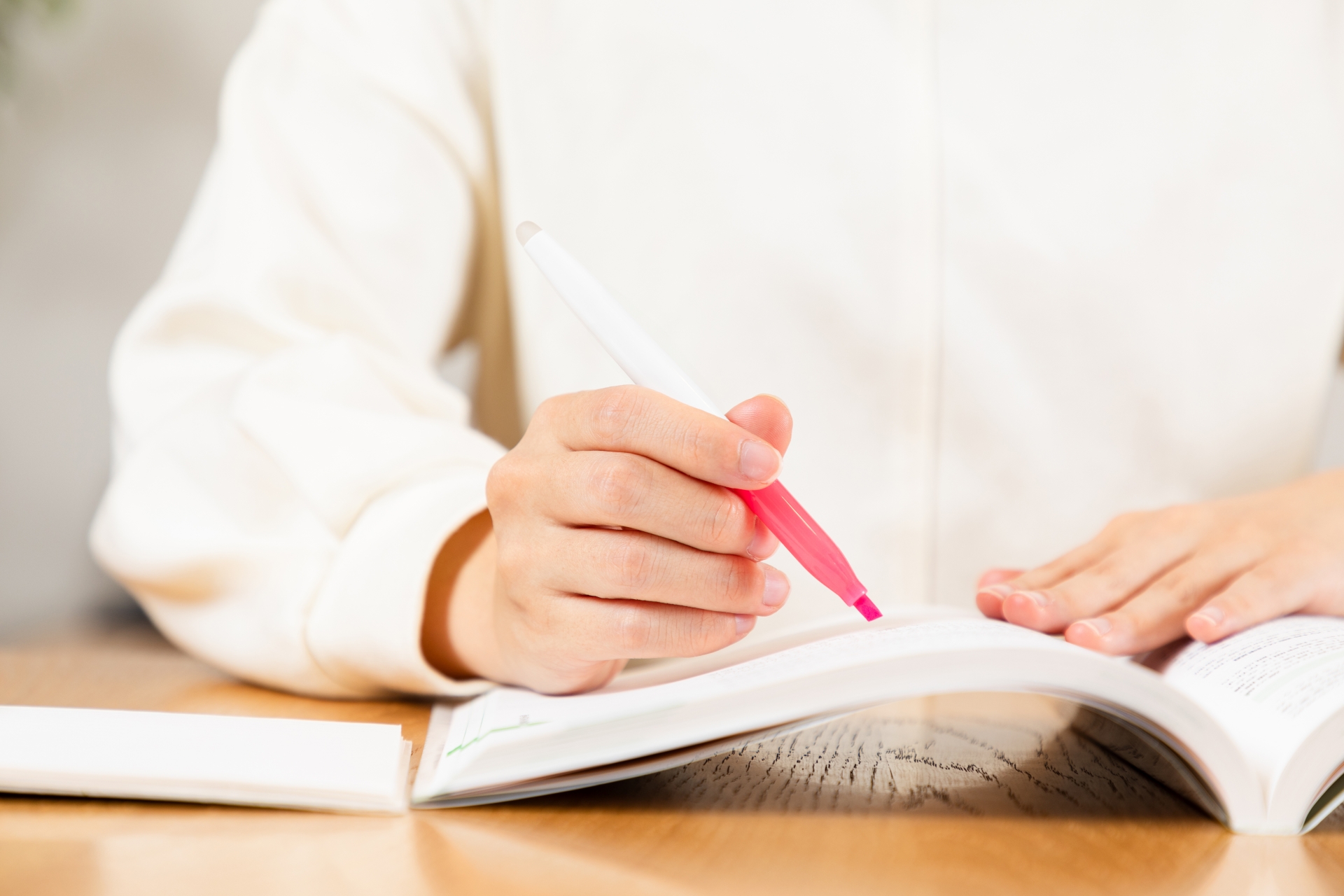
漢文の学習には、解説が詳しいものを選ぶことも重要です。
基礎的な句法の解説だけでなく、読解のポイントを丁寧に解説している問題集を選ぶと、漢文の文章のパターンを把握できます。
また、学習したいレベルの解説があるかどうかも、問題集を選ぶときのポイントです。
基礎を固めたい方は句法や重要語句の解説が詳しいもの、実力を上げたい方は問題や出題者の意図などの解説があるものを選ぶとよいでしょう。
解説は、明確でわかりやすい工夫がされているものだと学習が進みやすくなります。
辞書がわりになるものを選ぶ
漢文の学習をするには、辞書代わりになる参考書を選ぶこともポイントの一つです。
重要な単語や句法と、それらの解説が記載されている参考書なら、学習の際に容易に調べられます。
難関大学の過去問では、出題例が少ない句形について問われたことがあるため、共通テスト以外の試験対策にも有効です。
図解や見やすい字体を使っている参考書は、辞書がわりとして使用しやすいでしょう。
読みやすさも重視することで、情報量が多くとも調べやすくなるため、効率的に学習できます。
参考書選びが漢文を学習するうえで重要だとしても、適切に自分のレベルや志望校に合うものを選べるか、不安な方もいるかもしれません。
私たち横浜予備校は、独自にオリジナルの参考書やテキストを作成できるため、入試に特化した内容で短期間に効率よく実力をのばせることが強みです。
少人数制で指導を行っているほか、教科書を効率的に学べる自習支援や定期的な進捗確認など、徹底した学習管理が行われます。
生徒は学習習慣を身につけやすくなり、着実に成績を向上できるシステムになっています。
個別指導の徹底と各生徒に適したカリキュラムで、一人ひとりのレベルで無理なく学習が進められるだけでなく、個別ニーズや志望校に合わせた学習が可能です。
集中できる環境を整え、生徒に対して丁寧なサポートが提供できます。
横浜予備校では、生徒一人ひとりに合わせたプランで学習できるので、まずはご相談ください。
共通テスト漢文で満点を取る解き方

共通テスト漢文で、模試や過去問で読み飛ばしや勘に頼った解答をしてしまっていると、点数が安定しません。満点をとるには、問題の解答手順を理解して取り組む必要があります。
この章では、共通テスト漢文で満点をとるための流れを具体的に解説します。
リード文と注釈は必ず確認する
共通テストの漢文で満点をとるには、リード文と注釈を必ず確認することが大事です。
リード文とは、本文のはじめの部分に記載してあるあらすじのことです。
注釈とは、本文の最後に補足説明として書いてあります。
どちらも本文に関する重要な情報です。
本文を読む前に目を通しておくと、登場人物や本文までの流れなどがわかり、読解のヒントになります。
漢文でよく出題される時代の背景を勉強しておくと、リード文や注釈の情報を十分に活用できるでしょう。
本文を読む前に問題文を先に読む
本文を読む前に問題文を先に読んでおくことも、漢文を読むには重要な解き方の一つです。
問題文を先に読んでおけば本文の内容を大まかに理解できるだけでなく、問題文で尋ねられている内容に注意して読み進められます。
問題文には紛らわしいものもあるので、しっかり頭に入れてから本文を読むことが大切です。
しかし、選択肢も先に読むと間違った答えも目に入ってしまい、先入観で本文を読んでしまいます。
正確に問題を解くためにも、先に読むのは問題文だけにしておきましょう。
本文はいったん最後まで読む
漢文で満点をとるために、本文をいったん最後まで読むことも重要です。
本文は初めから読み、わからない部分があっても最後まで読み切りましょう。
漢文は最後で辻褄が合う場合が多く、読み終わってから解釈違いに気付くことがあります。
漢文はいったん最後まで読んでから、再度読み直して問題を解いていきましょう。
共通テスト漢文で満点を安定して取るために

共通テストの漢文は、配点は少ないものの、合格のためにはしっかり満点をとりたい科目です。
漢文を解くには句形の知識や読解力が必要であり、自分に合っている参考書でしっかり学習を進めましょう。
満点を安定してとるためには、限られた時間でどのように学習するか、試験ではどのような解き方をするかが重要です。
私たち横浜予備校では、1対1から1対4の少人数制で、特に多くのクラスでは1対2の形態でサポートを行っています。
少人数制にすることで、生徒一人ひとりのニーズや志望校に合わせた細やかなサポートができます。
学力に応じた個別カリキュラムや成果重視の学習プログラムを活用し、各生徒の成績向上に貢献することが可能です。
また、独自に作成した参考書やテキストを利用することで、入試に特化した内容を盛り込んで学習を効果的にサポートします。
生徒が先生に授業を行うプレゼン授業は、知識をしっかり定着させる効果があります。
横浜予備校は、生徒に合わせたプランで学習できるため、ぜひ遠慮なくご相談ください。
志望校合格に向けて、しっかりお手伝いさせていただきます。









