目次
大学受験の技術 読んで参考書・教科書を覚える方法

こんにちはヽ(^0^)ノ!佐藤です。
「社会の参考書を読んでも頭に入ってこないので書いたほうがいいですか?」という質問を受けました。読んで覚えるか、書いて覚えるかの選択には悩む人も多いと思います。
今回のコラムでは「読んで覚える方法」を中心にお伝えしていきます。
・読んで覚える方法をマスターすると良いこと
「書くと覚えられるのに読んだだけでは頭に入って来ない…」
「単語帳を何回も読んだ(見たのに)全然覚えられない…」
という人は多いのではないでしょうか?
確かに“書いて覚える”のと“読んで覚える”のとでは“書いて覚える”方が記憶に残りやすいですね。
しかし、この“書いて覚える方法”には弱点があります。
“読んで覚える”場合に比べて圧倒的に時間がかかってしまうのです。
そこで、ここぞという箇所では“書いて覚える”方法を、そうでない箇所では“読んで覚える方法”を使い分けていくといいですね。
書いて覚える方法
メリット:記憶に残りやすい
デメリット:時間がかかる
読んで覚える方法
メリット:時間が比較的かからない
デメリット:記憶に残りにくい
そこで、このコラムでは読んで覚える方法の“デメリット”である“記憶に残りにくい”を克服する術をお伝えしたいと思います。
このコラムが頑張る高校生・受験生のお役に立てれば幸いです。
読んで覚えるためのコツ
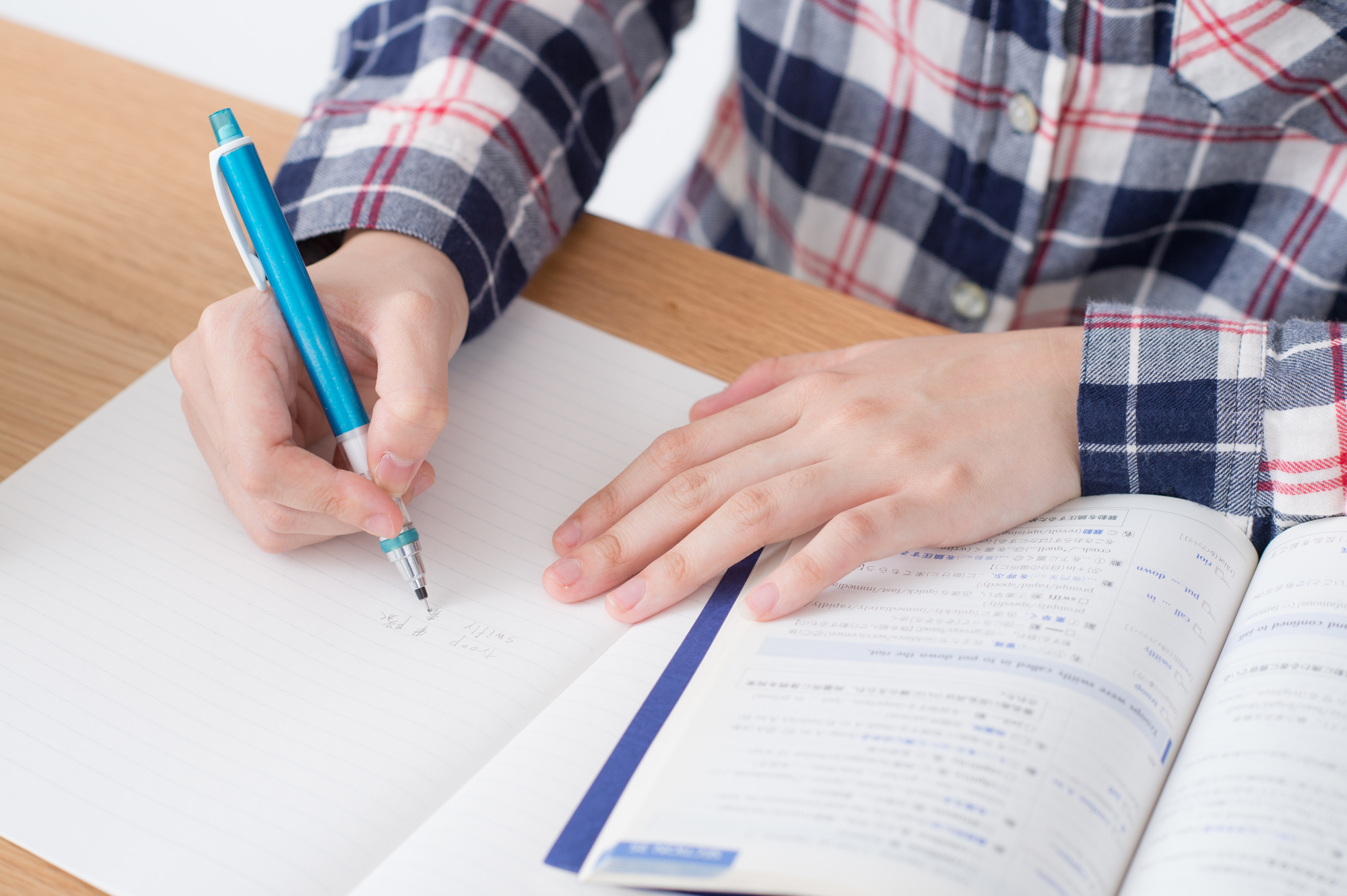
①目的を意識して読む速度を変える
歴史や公民、理科などの参考書を読む場合は理解するために①ゆっくりと2回程度読みます。
そして、理解ができれば概要を把握し頭の整理をするために極限までスピードを上げて(①の2倍程度のスピード)で3回ほど読みます。
そして、最後にキーワードを暗記するために③大事な箇所はじっくりと、そうでもないところはスピードをつけて抑揚をつけながら2回ほど読んでみましょう。
これで合計7回も同じものを読むことができます。
目的意識をはっきりとさせ読むスピードを意識しながらメリハリのついた勉強をしていきましょう。
②大声で読む(音読する)
暗記の得意な受験生が意外とやっているのがこの”大声で読む”方法。
「声に出すなんて小学生みたい…」
と思っている人は騙されたと思って是非、実践してみてください。
ただ読むだけでなく(視覚を使うだけ)、口も耳もフルに活用して暗記を行うことができます。
特に、社会科の教科書を覚えようとする際には適している方法です。
③利き腕ではない方の指を動かしながら読む
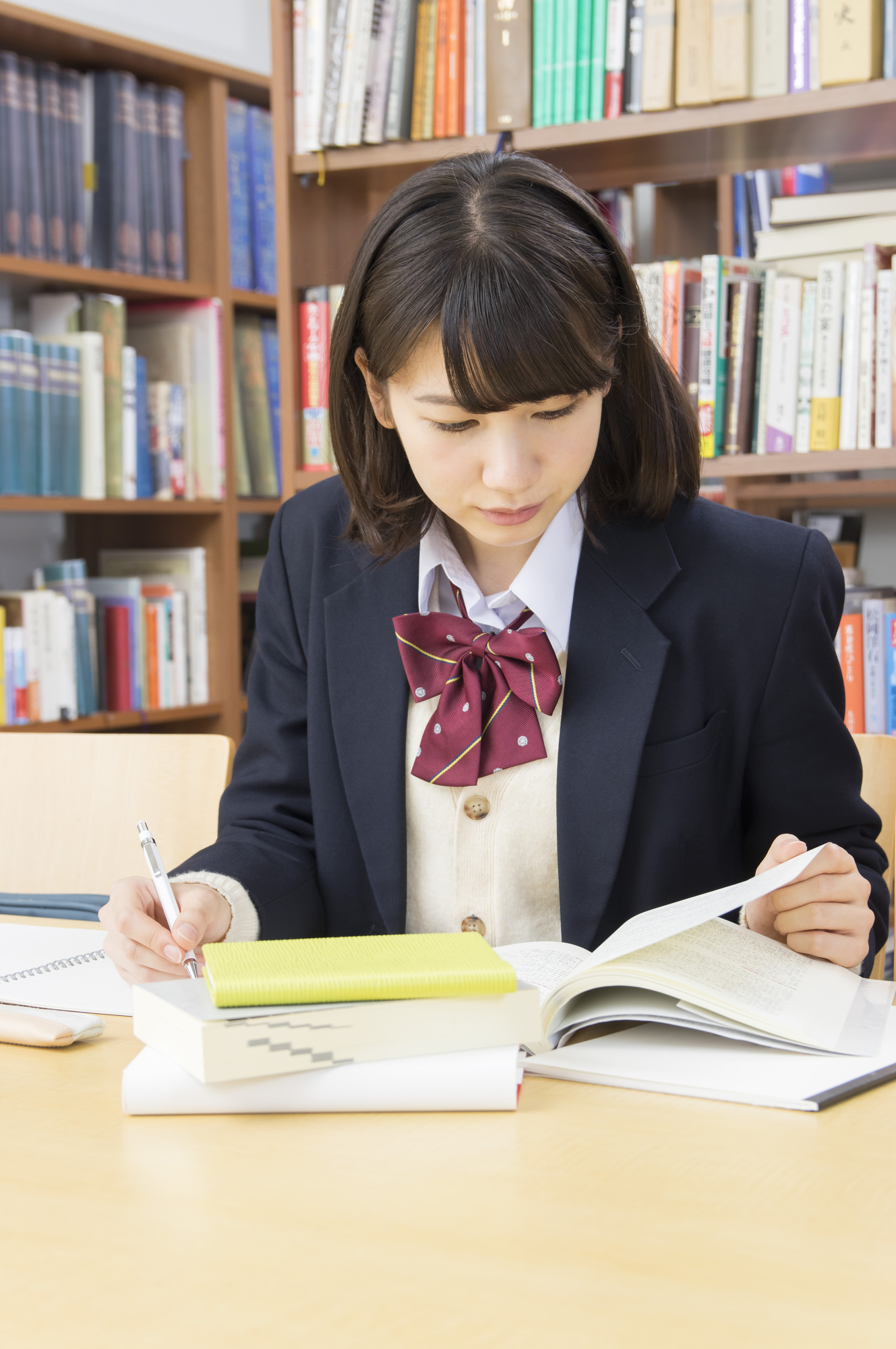
勉強や暗記をしているときは利き腕には意識は向きますが、利き腕ではない方の手にはあまり意識が向かないと思います。
利き腕でない方の指を動かしながら読むことで、右脳も左脳も働くようになり暗記効果を高めることができます。
④歩き回りながら読む
勉強は机の上だけでやるものではありません。
疲れてきたら体を動かしながら音読するようにしましょう。
頭だけでなく体の他の部位も刺激されるのでより暗記の効果は高まっていきます。
⑤ゆっくり3回よんで早口で2回読む
最初に紹介した①と②を合体させたもの。
特に英語の例文暗唱などに向いています。
声に出しながら覚えたいものを頭に染み込ませるようにゆっくりと3回、染み込んできたと思ったら頭をフル回転させながら早口で読んでみましょう。
教科書・参考書の読み方を工夫するだけでも他の受験生に大きく差をつける勉強ができるようになります。自分に合った方法をどんどん取り入れて効率のよい勉強をしていきましょう!









