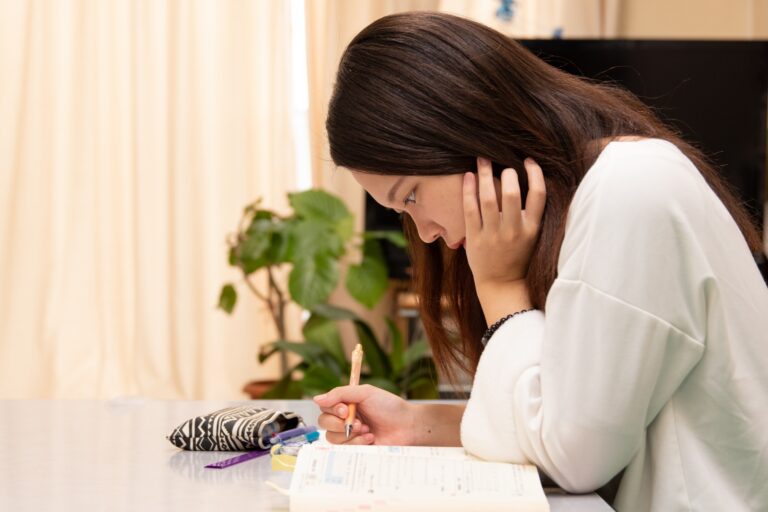現役の国立医大生に帝京大学医学部2018年度の実際の入試問題を解いてもらい、
各問題の率直な感想をもらい、問題分析をしてもらいました。
受験生の立場に非常に近い現役医大生の感想なので受験生の立場に近い感覚だと思います。
是非、参考にしてください。このコラムが受験生の皆さんのお役に立てれば幸いです。
帝京大学医学部2018「生物」入試問題分析|横浜の医学部予備校
分析と対策(2018年度、帝京大学 生物)
・300点満点で、合格最低点は217点とかなりの高得点
・競争率が40倍以上(47.8)とかなりの競争率の高さで、年々上がっている
・試験日は自由選択制
・一次選考合格者に限り、二次選考を行い、合否を判定する
・大問にして4つ、小問にして26問
・全体の難易度はやや易~難で、完答は難しいため、得意な分野から取り掛かるようにして、苦手な分野は一部分だけでも解くようにするなど、解ける問題から確実に解いた方が得点は上がる
・技能・知識はセンター試験レベルよりやや難しい程度で、得点は比較的難しい※複数日の問題がありますが、今回の分析は「数学社出版 2019年版 大学入試シリーズ 帝京大学(医学部)」の各教科の①を対象に行います。
以下、✩~✩✩✩で難易度を表します。
✩の数が増えるほど、難易度が高くなります。
第1問(1)✩ (2)✩✩✩ (3)✩✩ (4)✩✩ (5)✩ (6)✩✩
この大問は、免疫反応と疾患をテーマにした問題で構成されています。いかにも医学部っぽいですね。どこの学部においてもそうなのですが、大学入学後の勉強を意識した問題で構成されていることが多いのです。つまり、医学部受験者はワクチンなどを含む免疫・人体の構造・ホルモンについてはより重点的に学習しなければいけません。そのほかにも、臓器の役割や消化液の役割についても理解しておいてください。暗記系の問題に強い人にとっては最も得点しやすい大問だったでしょう。内容も難しくはありませんので、満点も夢ではありません。
対策としては、「医学部としてどのような視点が必要なのか?」ということです。ただ人体のことを暗記して、問題集が解けるようになればいいのでしょうか?合格した後も、難しい講義についていかなければなりません。医学部に合格するだけが目標ではありません、今から医学部生としての視点も大切にしておきましょう。
第2問(1)✩ (2)✩✩ (3)✩✩ (4)✩✩✩ (5)(6)(7)(8)
この大問は、光合成と細胞の代謝をテーマにした問題で構成されています。他の大問よりは医学部からは遠い問題でした。毎年大問1~2個分は、人体に深くは関わっていないように思えるものが出題されます。光合成は中学の頃から勉強している分野ですから、親しみはあるのでまだ解きやすかったでしょう。そして、実は解答の仕方のレパートリーも少なく、指示も丁寧なので、迷うことは少ないのです。ただ、光合成にやまをはる(重点的に学習する)受験生も少ないでしょう。それゆえに、難しく感じたかもしれませんね。医学部らしい問題だけでなく、幅広く様々な問題を復習しておくことがなによりの対策です。
第3問
(1)✩ (2)✩✩ (3)✩✩✩ (4)✩✩ (5)✩✩ (6)✩✩
この大問は、腎臓の構造と機能をテーマにした問題で構成されています。いかにも医学部という感じの問題でしたね。この問題を難なく解けた受験生は、合格した後も授業で得しますよ、と叫びたくるくらいに本当に大事な分野ではあります。「教科書には載っていないのでは…?」という内容のものがあり、それらはかろうじて教科書の本文の下の注意書きや研究のような発展的な内容を掲載するページにある程度でしょう。つまり、教科書だけでは対応が難しいと考えられます。生体内は複雑でありながら、現象が起こるメカニズムがかなりはっきりしていますから、資料集のように存分にページをとって細かく説明しているものを参考にしましょう。
対策としては、先ほど述べたように資料集を用いて学習することと、「医学部らしい問題」にたくさん触れておくことです。医学部は特殊な学科で、かなり偏差値も高いです。入学後の講義についていけなければお話にならないとでもいうように、この大問のように生体内のことの理解は入試時に確認されるのです。腎臓の働きは他の臓器に比べても複雑ではない方です、ぜひここで得点できるよう生体内反応を理解しておいてください。
第4問(1)✩✩ (2)✩✩ (3)✩✩✩
この大問は、真核生物の遺伝子発現調整をテーマにした問題で構成されています。今回の大問の中で、第4問が最も難しい大問だったのではないかと思います。生物の生体には深く関わっているのですが、医学部受験生がよく学習している範囲とは少しずれていますし、内容的にも難しかったように思います。また、問題文が長いので、設問にたどり着くまでに時間がかかってしまいます。また、実験問題は自分の知識よりも実験結果に忠実になって解き進めてください。
対策としては、多くの実験問題を解く事です。実験問題の特徴は、知識が必ずしも必要だというわけでないことです。今回の問題文を読んでもらえればわかると思いますが、実験の結果が問題の基礎になっています。つまりは、基本は実験からわかったことのみから考えます。そこに不必要な知識はいりません、必要な結果から推察することです(知識は答えを推測するヒントにする程度です)。
2018年度の帝京大学入試を、完璧に解ける人はかなり少ないように感じます。しかし、かなりの競争率の中で見事合格を勝ち取るためには苦手な出題形式は当然後回し、自分が得点出来るところからできる分だけ解いてなるべく得点を重ねていきましょう。生物は比較的簡単なので、難しい問題だと感じるもの以外は前から順番に解いていってもいいかもしれません。また、時間配分に気をつけて、終了五分前には空いているところを埋めることは忘れないでくださいね!同じ大学であれば好んでいる解き方や分野はありますので、入試本番でも模範解答の解き方は役に立つ可能性は高いです。ぜひその視点で過去問を分析してください。
入試問題は制限時間にシビアです。そのような状況では、解く順番が重要になります。順番を選ぶ基準としては、確実に得点できそうだと感じたものから解き、その中でも時間がかからなさそうなものから優先的に解きます。決める際の基準は「確実に得点できるか?」「短時間に解くことができるか?」になりますので、テスト開始後にはまず全体に目を通してどの問題から解くかを瞬時に判断しましょう。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
住所:神奈川県横浜市中区花咲町1丁目18番地
第一測量桜木町ビル5F
TEL:045-250-3915
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇