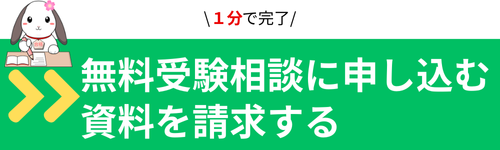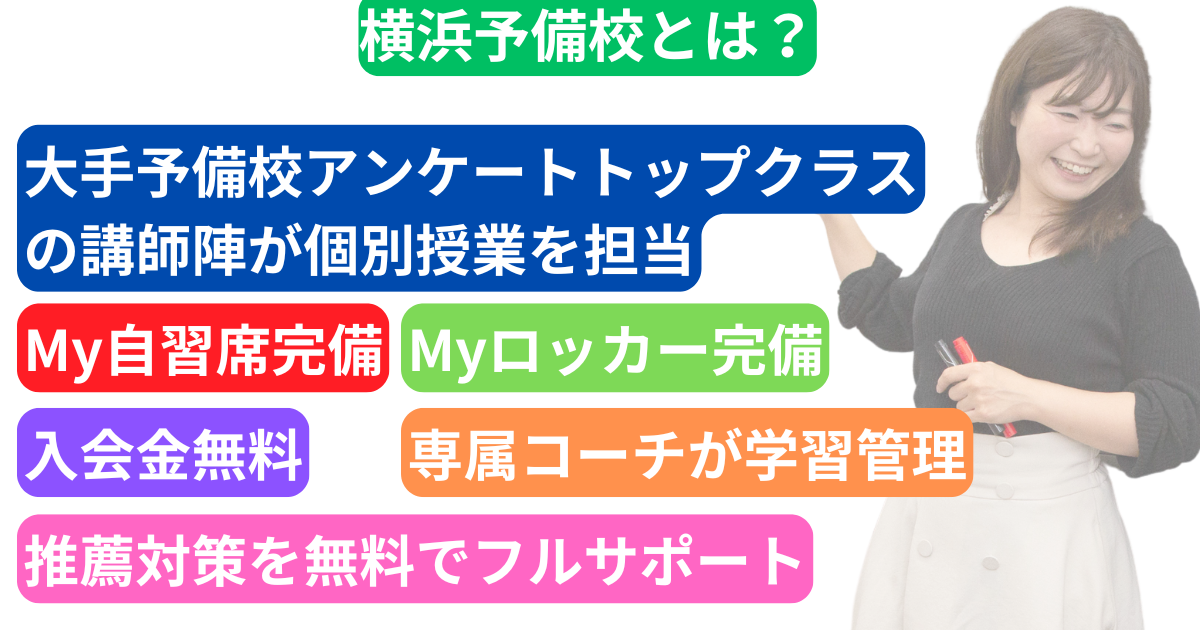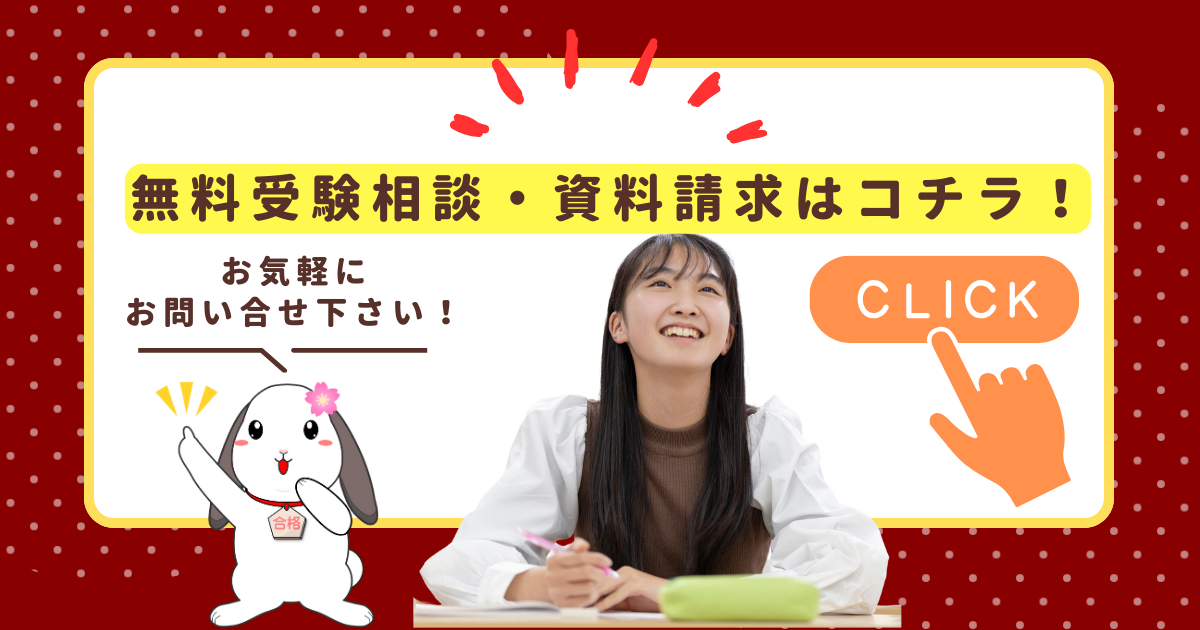難関大学の生物では、全く初見の実験について考察する問題が出題されることがあります。このようなタイプの問題に対応するためには、単なる暗記だけでは不十分で、それなりの対策が必要となります。今回は、生物の入試問題パターンを解説した上で、初見問題タイプに立ち向かえる実力を付ける方法を解説します。
目次
生物の入試問題パターン

生物の入試問題は、大きく分けて3つのパターンに分けられます。それぞれの特徴について簡単に紹介します。
基本知識問題
教科書や資料集にある基本的な知識を元にした穴埋め問題や、正誤判定問題がこれにあたります。生物の入試問題の中では最も簡単なパターンに分類されます。難易度が低い分、合格者の平均点も高くなることが予想されます。
典型問題
問題集にある典型問題の数字を変えただけのタイプです。計算が絡む問題は特に出題されやすいため、自分の志望校がこのタイプであると分かっているならば、対策もそれに合わせたものにすると良いです。
初見問題

難関大学で出題されることの多い形式です。受験生が見たこともないような実験を題材にしたリード文が与えられ、それを自力で分析した上で、その後の問題に答えていく形式です。設問の中に穴埋めによる知識問題が混ざることはありますが、基本的には記述式の考察問題が多いです。
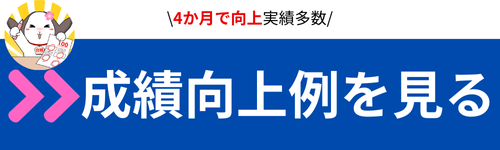
初見の考察問題問題を解けるようにするためには?

それでは続いて、難関大学で出題される初見問題への対策です。基本を疎かにしないことは当然として、その上で生物の問題を解くために必要な学習法について解説します。
丸暗記をしない
生物は暗記科目だと思っている人が多いですが、実はその考えが通用するのは、前述の基本知識問題しか出題されない場合のみです。最近では、共通テスト生物でさえ、知識問題が出題されず、厳しい時間制限の中で考察していかないと解けない問題が出題されています。暗記で知識を貯める際には、こういった考察問題に生かすことを意識して勉強しないといけません。具体的には、一つ一つの用語を点として覚えるのではなく、複数の用語の関連をイメージして、線や面として知識を蓄積していくことが重要です。ある単元の内容を、そこで登場する用語を複数絡めながら説明できるようになれば、十分にその単元のことが分かっていると言えます。
逆に、用語は覚えているものの、それらの関わりに対する理解が不十分である場合は、使いこなせる知識にはなっていないでしょう。用語集などに頼り切って勉強するのではなく、常に教科書や資料集の内容を関連させながら学習していくことが大切です。
問題文をよく読む

リード文が長くなると、内容を正しく把握することだけでも大変です。人によっては、時間制限があるためにざっくりとしか問題文を読まないことがあるかもしれませんが、それでは問題の重要なポイントを見逃す恐れがあります。基本的には、実験の流れを踏まえて少しずつ読み進めないと、何が大切な部分なのかはすぐには分からないように問題は作られています。そのため、焦って問題文を読むのではなく、丁寧に一語ずつ読んで、理解が不十分な状況にならないようにしたいです。理系受験生の中には、国語が極めて苦手な人がいます。そういった人は、特に意識して問題文を読む練習をしないと、1回読んだだけでは内容を理解できないかもしれません。自分の国語の力に不安があるならば、日頃から文章を読む訓練をしないといけません。
自分の知識と照らし合わせる
初見の実験を扱った問題でも、基本的には高校生の学習指導要領には沿ったものであるはずです。そのため、既存の知識をうまく応用していけば、必ず解答の糸口が見えてきます。ここで重要なのは、その問題がどの単元に関連する問題であるかを見抜くことです。呼吸や光合成といった代謝に関連する実験であれば、教科書の代謝の範囲で出てきた内容を思い出せば解答の役に立つはずです。他の分野も同様で、まずは自分が持っている知識のうちのどの部分を使えば解答に近づけるかを考えるべきです。
それが分かったら、さらに内容を深掘りしていきます。未知の物質の名前が出てくることもよくありますが、そのような場合も、今までに学習した範囲と必ず対応しているはずなので、自分の知識とよく照らし合わせて考えるようにしましょう。
正確な記述を心がける

初見の実験を読み解く問題では、記述式の設問もあります。このような問題は配点が高いことが予想されるため、正解できるかどうかが合否の鍵になります。記述式問題のポイントは、必要な要素を過不足なくまとめることです。自分の中でさまざまな知識が関連づけられていると、うまく言葉を選ぶことができて、結果としてすっきりとした見やすい答案に繋がります。
逆に、知識が整理されていないと、リード文から言葉を抜き出して繋げただけの解答になりがちです。当然後者では点数がもらえる可能性が低くなります。日頃から、自分の言葉で分かりやすく記述する練習をしましょう。
まとめ