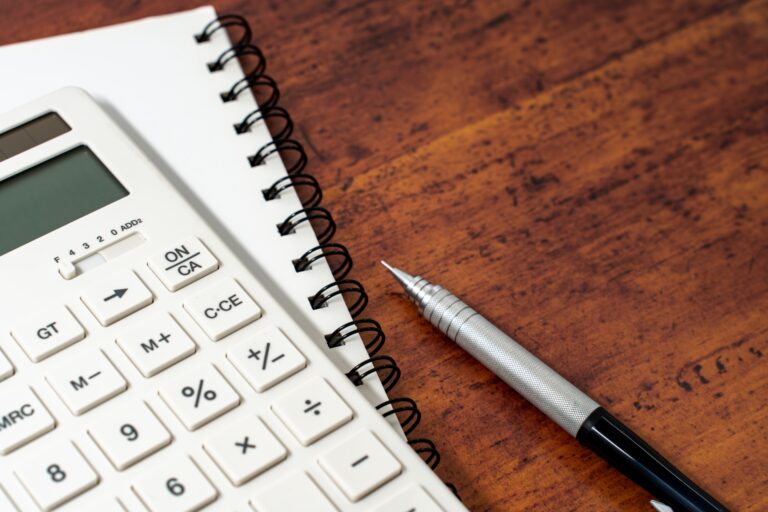
大学受験にかかる費用には、出願料や参考書代だけでなく、模試・交通費・宿泊費なども含まれます。
しかし、具体的な金額や内訳が分からず、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、大学受験に必要な費用の詳細や大学ごとの違いを解説します。
また、受験費用を抑える方法も紹介するので、計画的に準備を進めるための参考にしてください。
目次
大学受験にかかる平均費用はどのくらい?

大学受験には、出願費用だけでなく交通費や宿泊費、さらには入学しない大学への納付金など多くの費用が発生します。
日本政策金融公庫の調査によると、大学受験にかかった費用は平均約390,000〜420,000円です。
これに加えて、合格した大学への入学料や授業料がかかってきます。また、国公立と私立の違いや受験する大学数によっても費用差は出てきます。
大学受験にかかる費用項目
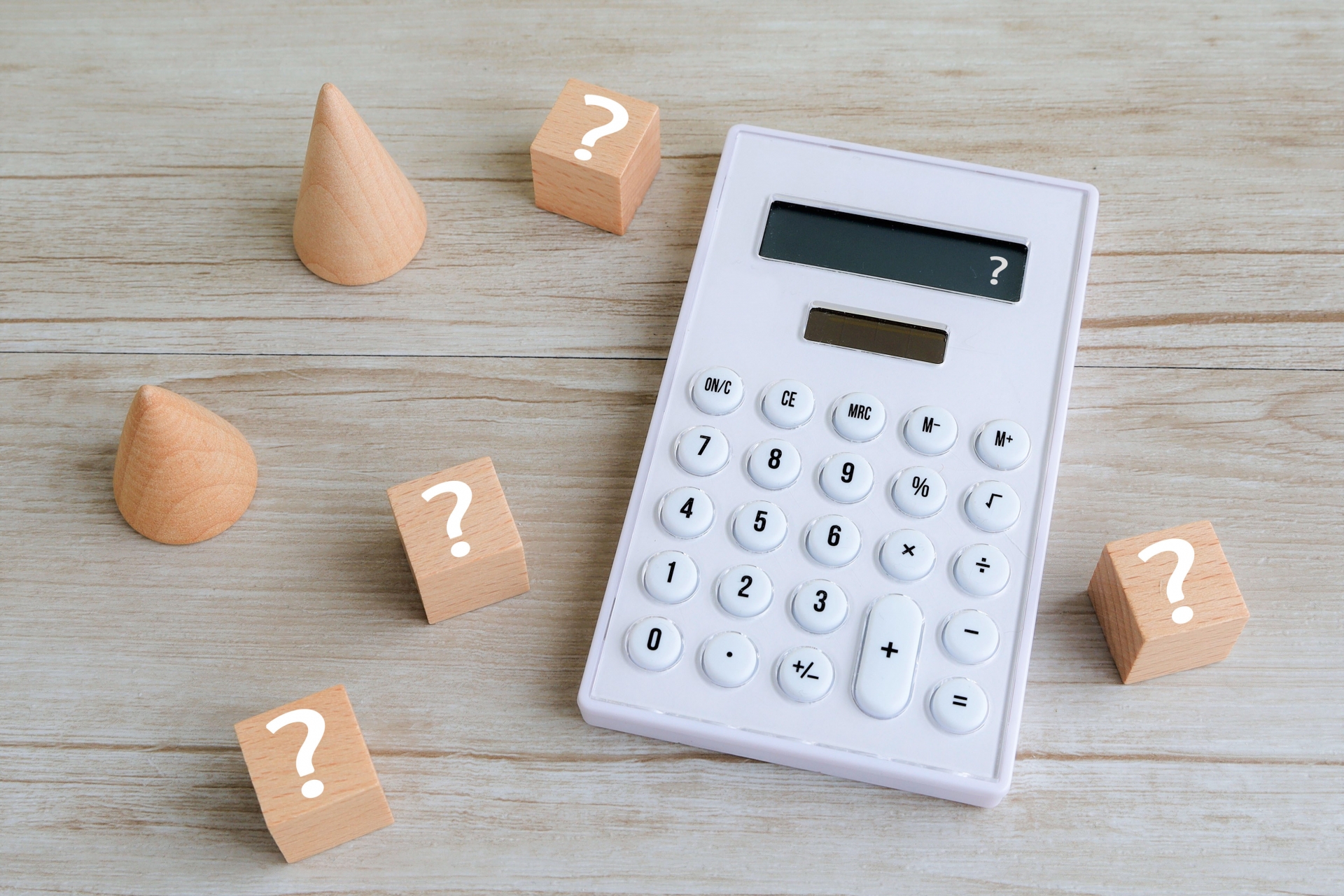
大学受験にかかる費用項目には下記のようなものがあります。
・受験料
・入学料
・授業料
・入学しなかった合格大学への納付金
・大学受験に伴う交通費や宿泊費
具体的にどの項目にどのくらいの費用がかかるのかを見ていきましょう。
受験料
大学受験には受験料(入学検定料)が必要です。受験する大学・学部ごとに納めるため、併願数が多い程負担も大きくなります。
大学入試の方式には一般選抜・学校推薦型選抜・総合型選抜などがありますが、どの方式でも1回の受験ごとに費用が発生します。
まず大学入学共通テストの受験料は3教科以上で18,000円、2教科以下で12,000円です。
国公立大学の一般選抜(二次試験)の受験料は約17,000円で、前期・後期と受験する場合はそれぞれ納める必要があります。
私立大学の一般選抜の受験料は約35,000円です。大学によって異なりますが、同じ大学内で別の学部を受験する場合(学内併願)も、それぞれ受験料がかかります。
ただし、2学部目以降の受験料を割引する制度を設けている大学もあるため、事前に各大学の制度を確認しておくとよいでしょう。
医学部や歯学部は特に高額で、約40,000〜60,000円となることが一般的です。
近年、私立大学で増えている大学入学共通テスト利用入試は、受験料が約15,000〜20,000円と一般選抜よりも安く抑えられます。この方式では、共通テストの成績を活用するため大学独自の試験を受ける必要がありません。
また受験料以外にも、願書請求費用や各種証明書の発行手数料・郵送代などがかかります。最近はインターネット出願が主流ですが、印刷や郵送が必要な場合もあるため意外と見落としがちな出費です。
入学料

大学に合格すると、合格発表後1〜2週間以内に入学金を納付する必要があります。入学金は大学に入学する権利を確保するための費用であり、期日までに納付しないと、入学権利を失ってしまいます。
特に国公立大学が第一志望の場合、国公立の合格発表は遅いため、それまでに合格した私立大学の入学金を納付しなければならないことがあるでしょう。国公立に合格すれば、私立大学へ支払った入学金は無駄になってしまうため、慎重に併願計画を立てることが大切です。
併願校への入学金の納付に関しては、入学しなかった合格大学への納付金の見出しで詳しく解説します。
入学金の金額は大学の種類によって異なります。国立大学は文部科学省の標準額により、ほとんどの大学で282,000円です。夜間部では、入学金が半額程度に設定されている場合もあります。
公立大学は国立大学と同程度ですが、地域内か地域外かで金額が異なる点が特徴です。
文部科学省による2023年度学生納付金調査結果によると地域内入学者の入学金の平均は224,066円、地域外入学者の入学金の平均は374,371円と、出身地によって負担額が大きく変わります。
私立大学は学部によって入学金に差があり、文系学部は約225,000円、理系学部は約250,000円が平均的です。医歯系学部は特に高額で、1,000,000〜2,000,000円となることもあります。
授業料
入学手続きでは、入学金のほかに、施設設備費・実験実習費などの諸費用と、前期分の授業料を納める必要があります。
国公立大学と私立大学では授業料の仕組みが異なり、特に私立大学は学部ごとに金額が大きく変わることが特徴です。
国立大学の授業料は文部科学省が定めた標準額に基づいて決められています。ほとんどの国立大学で年間の授業料は、535,800円です。公立大学の授業料は、国立大学の標準額と同程度です。
私立大学の授業料は国公立大学とは異なり、各大学が独自に決めています。そのため、大学や学部によって金額に大きな差があります。文系学部の年間の授業料は827,135円、理系学部は1,162,738円、医歯系学部は2,863,713円です。
入学しなかった合格大学への納付金

大学受験では、第一志望校のほかに併願校を受験するのが一般的です。しかし、気をつけなければならないのが併願校の入学金の納入期限です。
多くの私立大学では、第一志望校の合格発表前に入学金の支払い期限が来ることがあります。この場合、第一志望校の合否がわからないまま、併願校の入学金を支払わなければいけません。
もし入学金を納めなければ、たとえ合格していても入学する権利を失ってしまうため、万が一第一志望校に不合格だった場合のリスクを考え入学金を支払います。しかしその後第一志望校に合格すれば、併願校には入学しない場合でも納めた入学金は返金されません。
大学によっては、一定の条件を満たせば入学金の納付期限を延ばしてくれる場合もあるため、事前に確認しておくとよいでしょう。大学受験は、学力対策だけでなく、学費や奨学金の計画も重要なポイントになります。
「どの大学が自分に合っているのか」「学費を抑える方法はあるのか」など、進学に関する不安がある方は、ぜひ横浜予備校の無料相談をご活用ください。
横浜予備校では、大学受験対策だけでなく、学費や奨学金に関する相談にも対応しており、プロの講師があなたの進学をトータルでサポートします。 受験に向けた万全の準備を整え、納得のいく進路選択をしましょう。
大学受験に伴う交通費や宿泊費
大学受験では、受験会場までの移動に交通費がかかります。近場の大学を受験する場合は負担が少なく済みますが、遠方の大学を受験する場合、新幹線や飛行機の利用で費用が高額になることがあります。
特に地方から都市部の大学を受験する場合は、往復で数万円かかることも珍しくありません。交通費を抑えるためには、早めにチケットを予約し早特や早割などの割引を活用するとよいでしょう。
また、受験当日の移動では交通機関の遅延などのリスクも考慮する必要があります。試験当日に慌てないように前泊するケースもあります。特に、朝早くから試験がある場合や連日異なる大学を受験する場合は、ホテルを利用することで落ち着いて受験に臨めるでしょう。
宿泊費は宿泊する地域やホテルのグレードによって異なりますが、一般的なビジネスホテルで1泊あたり7,000円〜10,000円程度が相場です。
受験シーズンには受験生向けの割引プランを用意しているホテルもあります。ただし、これらのプランはすぐに予約が埋まるため、受験日程が決まったら早めに宿泊先を確保しましょう。
さらに、複数の大学を受験する場合は試験日程を調整し、宿泊日数をできるだけ少なくする工夫も大切です。
大学・学部別の受験の平均費用
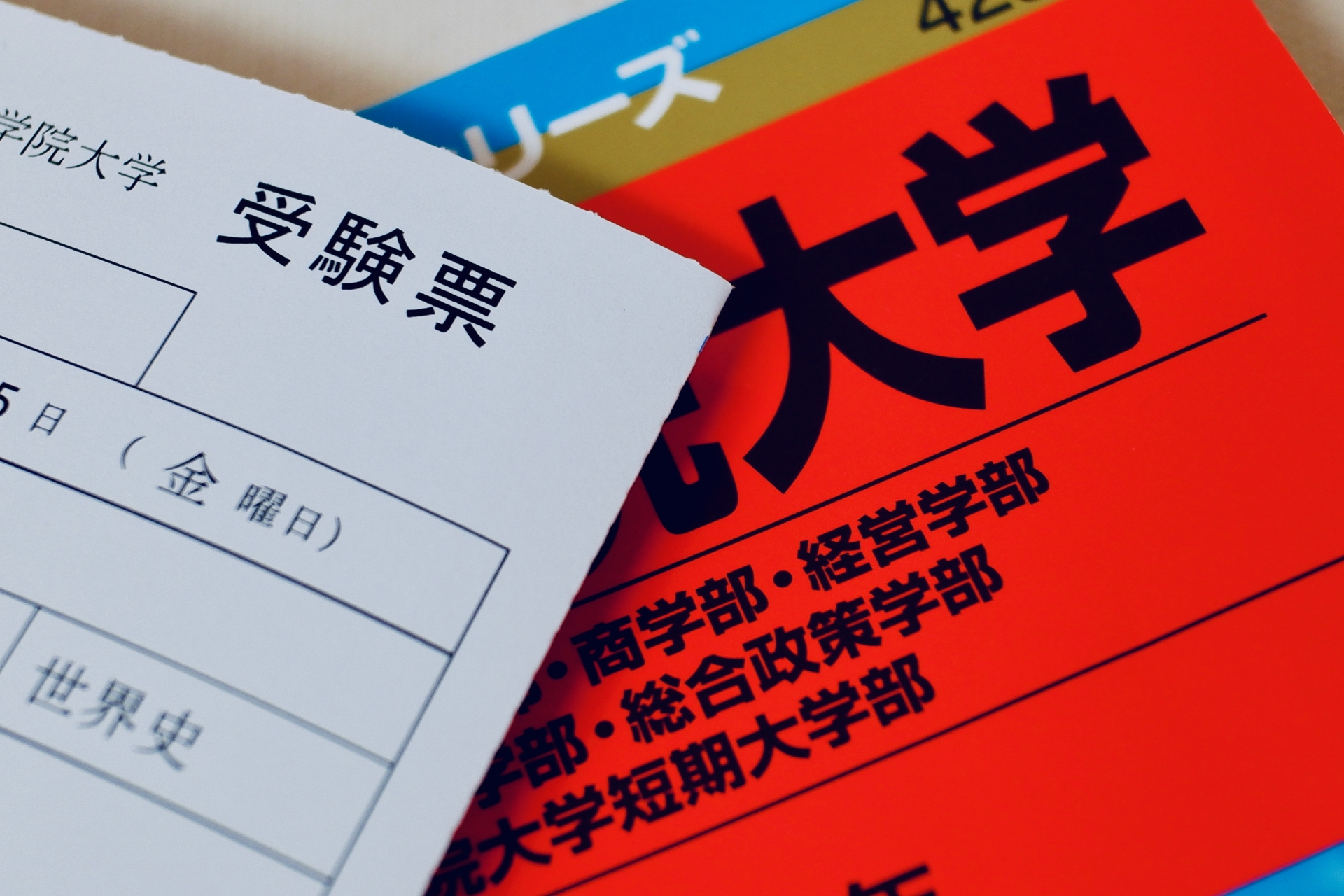
大学受験にかかる費用は志望する大学や学部によって大きく異なります。
特に、国公立大学と私立大学では受験料や学費に差があり、理系は文系よりも費用が高くなる傾向があります。
国公立大学は受験料が安いものの、大学入学共通テストの受験が必須です。一方、私立大学は受験料が高めで、理系は授業料も割高になります。
国公立大学文系
国公立大学の文系を受験する場合の具体的な受験料は以下のとおりです。
・大学入学共通テストの受験料は3教科以上で18,000円、2教科以下で12,000円
・国公立大学の一般選抜(二次試験)の受験料は約17,000円
よって、29,000円〜35,000円が必要となります。前期と後期をそれぞれ受験する場合は受験料約17,000円をその都度納める必要があります。
国公立大学理系
国公立大学の理系を受験する場合も文系と同じ額の受験料が必要ですが、理系の場合は大学入学共通テストを2教科で受験できる学部はほとんどありません。
・大学入学共通テストの受験料は3教科以上で18,000円
・国公立大学の一般選抜(二次試験)の受験料は約17,000円
ほとんどの大学で35,000円が必要となり、前期と後期でそれぞれ、受験料約17,000円を支払います。
私立大学文系
私立大学の一般選抜の受験料は約35,000円です。大学入学共通テスト利用入試を導入している場合は、受験料が約15,000〜20,000円と一般選抜よりも安く抑えられます。
私立大学理系
医学部や歯学部の受験料は特に高額で、約40,000〜60,000円が一般的です。
大学受験費用を抑える方法

大学受験には、受験料・交通費・宿泊費などさまざまな費用がかかります。しかし、工夫次第で無駄な出費を抑えることが可能です。
受験する大学を精査する
受験する大学を増やす程、受験料・交通費・宿泊費などの費用がかさみます。また複数の大学に合格した場合、入学権利を維持するためにいくつかの大学の入学金を納める必要があり、結果として負担が大きくなります。
そのため、志望度の高い大学を中心に受験校を厳選することが大切です。併願校であっても、本当に自分がその大学や学部で学びたいのか、納得できる大学を選びましょう。
共通テスト利用入試を活用する
共通テスト利用入試を活用すれば、受験費用を抑えることができます。この方式では、大学入学共通テストの結果をもとに合否を判定するため、一般選抜よりも安く受験できます。
例えば、私立大学の個別受験は1出願あたり約35,000円かかるのに対し、共通テスト利用入試なら15,000〜20,000円程度に設定されている大学がほとんどです。
また、共通テストは全国各地で実施されるため、遠方の大学を受験する場合でも移動の負担を減らせる点もメリットです。交通費や宿泊費を抑えることも可能でしょう。
ただし、共通テストのみで合否が決まる方式は競争率が高く、合格ラインも厳しく設定されていることがあります。
学内併願割引を活用する
学内併願割引は、私立大学で実施される、同じ大学内で複数学部を受験する場合に受験料が割引される制度です。志望校が決まっているものの、学部選びに迷っている方に有効です。
例えば通常の個別受験では1学部あたり約35,000円の受験料がかかりますが、学内併願割引を利用すると、2学部目以降の受験料が15,000円〜25,000円程度に割引されることがあります。
横浜予備校では、受験生一人ひとりに適切な受験プランを提案し、学内併願割引の活用方法や、効果的な併願校選びをサポートしています。
少人数制(1クラス平均2名)の個別指導を採用し、一人ひとりの状況を把握しながら、受験戦略のアドバイスを行います。
さらに、志望校の出題傾向を分析し、学内併願割引を活用しながら、合格の可能性を引き出す受験プランを作成します。
また、横浜予備校では、受験対策だけでなく、出願戦略や学費相談にも対応しており、受験生と保護者の皆様をトータルでサポートします。
どの受験方式が自分に合っているのか、学内併願割引を活用して受験費用を抑えたい、第一志望合格のための適切な戦略を知りたいと考えている方は、ぜひ横浜予備校の無料相談をご利用ください。
プロの講師陣が、あなたの志望校合格を全力でサポートします!
併願校は合格発表日を踏まえて効率的に出願する
大学受験では、併願校であっても合格した大学の入学金を納める必要があります。ただし、一度支払った入学金は基本的に返金されないため、できるだけ不要な支払いを避ける工夫が大切です。
そのため、受験する大学を選ぶ際には入試日程だけでなく、合格発表日と入学手続きの締切日の確認が重要になります。
第一志望の合格発表を待たずに併願校の入学金を納めると、結果次第では不要な出費となる可能性があります。ですので、下記のような対策も考えておきましょう。
・第一志望校の合格発表より後に入学手続きの締切がある大学を選ぶ
・同じ大学でも合格発表の早い入試方式を活用する
・共通テスト利用方式を併用し個別試験の回数を減らす
これらの対策を活用することで、無駄な入学金の支払いを抑えながら、第一志望校への進学の可能性を広げることができます。 事前に各大学のスケジュールを確認し、受験計画をしっかり立てることが大切です。
大学受験費用を抑えて志望校へ合格するために
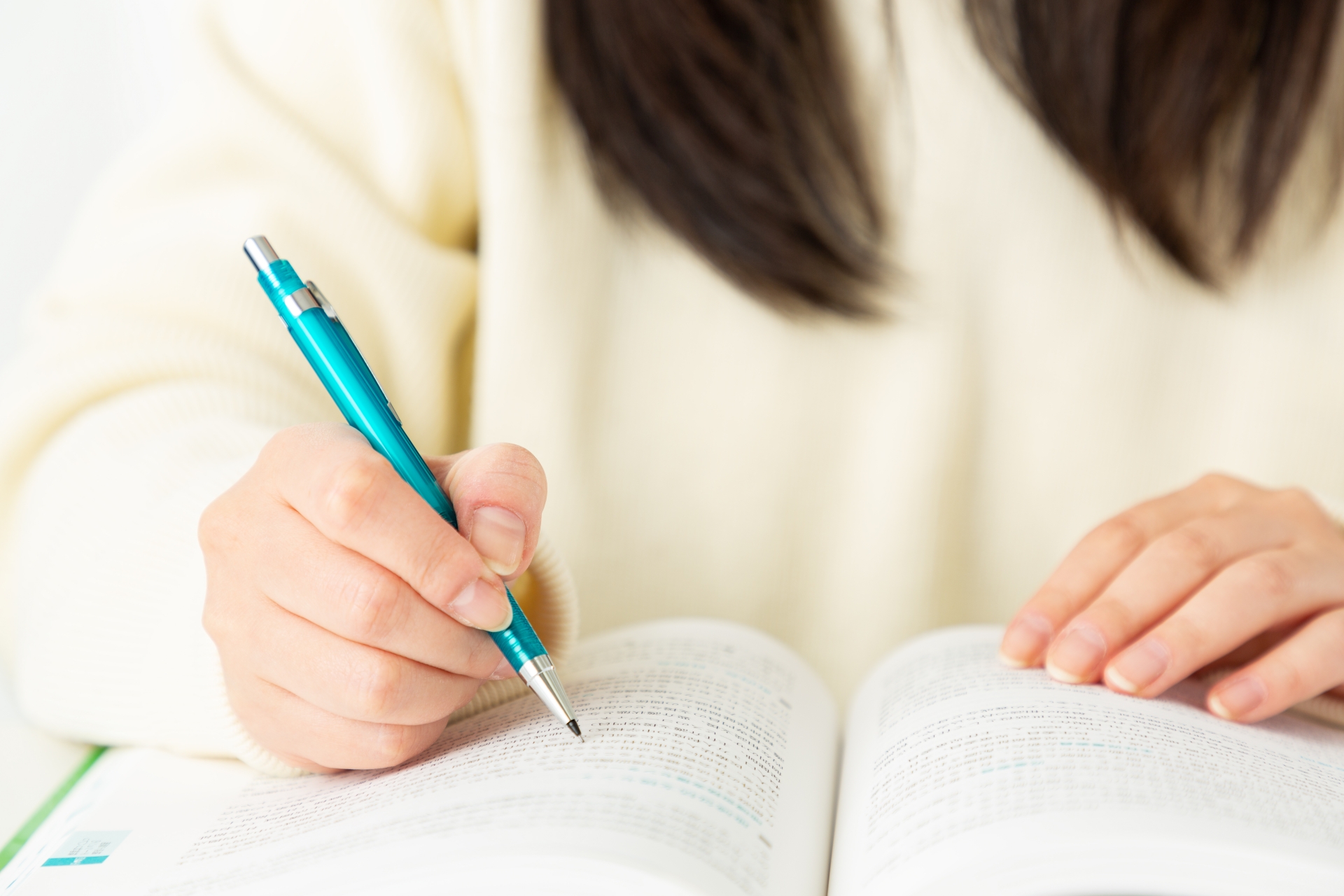
大学受験には、さまざまな費用がかかります。
受験費用を抑えるためには、受験校を厳選し、共通テスト利用入試や学内併願割引を活用することが有効です。
また、併願校の合格発表日を確認し、入学金の支払いを最小限に抑える戦略を立てることも重要です。
受験計画を立てる際は、費用を考慮しながら、無駄な出費を避ける方法を取り入れることで、志望校合格に向けた受験費用を効率的に管理できます。
横浜予備校では、大学受験にかかる費用についてのご相談も承っており、受験生や保護者の方が安心して受験準備を進められるようサポートしています。
受験費用の削減方法や、適切な受験プランの立て方についてお悩みの方は、ぜひ横浜予備校の無料相談をご活用ください。 プロの講師が、一人ひとりに合った受験計画をご提案し、志望校合格をサポートいたします。











