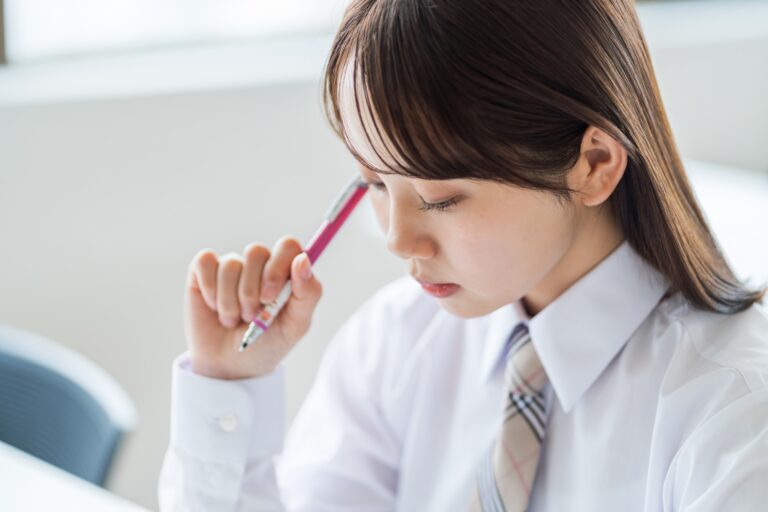現役生や浪人生が医学部合格を目指す際、二次試験の重要性を感じる方が多いでしょう。一次試験を通過した精鋭たちがさらに選ばれるため、厳しい競争の選抜になります。この段階での不安や焦りは、受験生にとって避けがたいものです。
早めに志望校を決定して、過去問やインターネットを活用し、出題傾向や足切りラインを把握することが重要です。
本記事では、医学部試験の特徴や国公立と私立の違い、そして対策方法について紹介します。医師を目指す受験生にとって、役立つ情報をお届けします。
目次
医学部の二次試験の特徴

はじめに、二次試験の一般的な特徴を把握しましょう。
個別の学習に進むのは、この概要を理解した後でも遅くはありません。
高い学力が必要
医学部の二次試験はとても難易度が高く、合格するためには優れた学力が求められます。
特に国公立大学の医学部試験を突破するためには、偏差値65程度が目安とされています。
これは、試験結果がよい順に並べた際に、上位約5%に入らないと達成できない数値です。
特に、東京大学・東北大学・京都大学などの旧帝大医学部を受験する場合、さらに高い偏差値が必要となります。
小論文を課されることもある
医学部の二次試験には、小論文が課されることがあります。
小論文の形式には、問題文に対して自分の考えを述べる「テーマ型」や、図表や長文を読解し、要点をまとめる「資料読解型」などがあります。
これらは、私立の医学部に限らず、国公立の医学部の二次試験にも含まれる場合があります。
なお、試験は前期と後期の日程に分かれて実施されることが一般的ですが、前期試験が基本的に行われることが多いです。
国公立の医学部の場合、一次試験の代わりに共通テストの結果が評価され、さらに二次試験の学力検査や面接が総合的に判断されて合否が決定されます。
学力検査が行われる

医学部の二次試験では、大学や学部独自の学力検査が必須となります。
小論文とは異なり、学力検査は前期日程でも後期日程でも必ず実施される試験形式です。
学力検査の科目は、英語・数学・理科で構成されており、一部の大学では国語も含まれる場合があります。例えば、東京大学の二次試験の内訳は以下のとおりです。
・国語:国語総合、国語表現
・数学:数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学A、数学B
・理科:地学基礎・地学、生物基礎・生物、化学基礎・化学、物理基礎・物理
・外国語:コミュニケーション英語I、II、III
また、京都大学の二次試験では、国語に古典が出題され、外国語には英語以外にドイツ語・フランス語・中国語から選べるというユニークな制度を設けています。
国公立大学と私立大学医学部の二次試験の違い

同じ医学部の二次試験でも、国公立大学と私立大学には大きな違いがあります。
試験の日程や回数、試験内容、共通テストの利用の有無について解説します。
試験日程や回数の違い
私立大学の医学部入試は、大学や学部ごとに別々の日程で実施されます。受験日が重ならなければ、併願しても問題はありません。
一方、国公立大学の医学部入試は、共通テストと前期の一般試験の全校統一日程で行われます。
後期試験の仕組みもありますが、倍率が大幅に上がるため、前期試験の一発勝負と考えるべきです。
私立入試では複数回のチャンスがあり、一度でも合格すれば念願の医学部入学が可能ですが、国公立入試は一度失敗すると後がないため、試験当日のプレッシャーが大きく異なります。
試験内容の違い
私立の医学部入試では、マークシート形式の穴埋め式問題が出題されることが大半ですが、国公立の医学部では、論述式の回答が求められます。
一方、科目の内訳には大きな違いはなく、ほとんどの大学や学部が、英語・数学・理科の科目で構成されています。
共通テスト利用可否の違い

国公立大学の医学部入試は、例年1月中旬に行われる共通テストの結果をもとに、受験資格が判定されます。
各大学が独自に定めた足切り基準を下回った場合、その受験生は足切りとなり、二次試験に進むことができません。
一般的に、ボーダーラインの目安はおおむね80%です。私立大学の医学部入試は、大学ごとに独自で実施される一次試験と二次試験から構成されることが一般的です。
志望校が明確である場合、共通テストを受験しない選択をする受験生も珍しくありません。
しかし近年、私立大学では共通テスト利用選抜という仕組みが導入されており、共通テストの結果が選考基準に影響を与えることがあります。
・学力テストで80~85%の得点率を達成できる見込みがあること
・医学部進学に必要な学費を確保できること
上記の2つの条件を満たす方は、志望校の制度に応じて、共通テストの得点のみを合否の判定基準とする「単独型」、または大学独自の試験結果とともに合算して判定する「併用型」のいずれかを選択することができます。
医学部の二次試験に合格するための対策

医学部の二次試験の仕組みが理解できた方は、早速対策に取り組みましょう。
合格を目指すための有効な対策手順を以下にまとめました。
足切りラインのチェックを行う
まずは、大学や学部別に設けられた足切りラインを確認しましょう。
医学部入試のボーダーラインは、おおむね80%を下限とし、上位の国公立大学では90%以上の得点率が必要となる場合もあります。
足切りラインの定義は、最終的な合格率が50%になる得点率です。
例えば、85%の正答率を確保した学生のうち、二次試験の面接や小論文、学力検査を通過した学生の半分以上が合格することが多いです。
足切りラインを下回った場合でも、即座に不合格が確定するわけではありません。二次試験の学力検査の結果によっては、挽回のチャンスがあります。
日程の確認
私立大学を先願で受験する場合や、国公立大学が第一志望で私立を保険として受験する場合は、試験日程の確認が欠かせません。
併願は万一のリスクヘッジには有効ですが、個別の受験対策やスケジュール管理の負担が増えることに注意が必要です。
また、試験日程が重なることによって、一次試験に合格しても二次試験の受験ができなくなるという勿体ない事態が発生する可能性もあります。
試験科目を把握する
志望校の情報収集を早急に行い、試験科目を早めに把握しましょう。
基本的には、外国語・数学・理科(二科目)が求められますが、私立大学の医学部を中心に、志望校ごとに特徴や違いがある場合があります。
例えば、弘前大学の医学部では総合問題という独特な形式の問題が出題されます。また、二次試験に理科系の科目を設けない大学も少なくありません。
志望校の試験科目を早期に把握し、注力すべき分野や単元を特定して、無駄のない学習につなげましょう。
配点の差を確認し優先度を決める
各科目の配点の違いを確認し、重点的に対策すべき領域を特定します。
全科目で高得点を確保することが理想ですが、苦手科目や得意科目に差が出ることが一般的です。
特に不得意な科目の配点が高い大学に関しては、受験を諦めるか、優先度を下げて他の大学との併願を検討するなど、戦略的な対策が求められます。
例えば、東京大学医学部の二次試験は4教科5科目440点満点で、数学・理科・英語が120点ずつのウェイトを占め、残りの80点は国語に配分されています。
一方、京都大学の二次試験では4教科5科目1,000点満点で、英語と外国語がそれぞれ300点ずつの比率となっており、配点に大きな差があるのが特長です。
試験科目の出題傾向を把握し対策する
最後に、試験科目の出題傾向を把握し、志望校別に特化した対策を立てましょう。
重要なのは、小論文で問われる出題形式や面接でよく聞かれる質問、学力検査の出題形式です。
例えば、東京大学の場合、英文の要約や文脈の把握、和訳や読解総合問題に分かれています。英作文では、問いに対する回答や意見を端的にまとめる問題が出題されます。
求められる語彙は高い水準ですが、専門的な用語には注釈がつくため、対策を立てやすい試験です。
一方、京都大学では、長文の下線部の和訳や自由英作文の出題があります。
長文読解は歴史・哲学・化学など専門的で抽象的な英文が引用され、記述の回答には豊富な語彙が求められるため、難易度は高めです。
このように、同じ英語でも志望校によって出題の傾向や難易度に違いがあるため、志望校に特化した対策が欠かせません。
横浜予備校では、難関大学や医学部を目指す受験生に向けて、専門性の高いカリキュラムと専用コースを用意しています。
1クラス最大4名までの少人数制と、個別対応の仕組みによって、生徒それぞれの志望校や学力に合わせたきめ細やかなサポートが可能です。
また、学習の進捗状況を踏まえた定期的なアドバイスや学習計画の見直しも行い、目標達成に向けて一人ひとりを丁寧に支援しています。
効率よく成果を上げるための学習環境をお探しの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
医学部の二次試験の勉強方法

共通テストの足切りラインを突破しても、まだ安心してはいけません。
志望校ごとに出題形式が異なる二次試験は、これまでの試験よりも一層対策が難しくなるためです。
学力検査、面接、小論文の試験科目ごとに効果的な勉強方法を解説します。
学力検査の勉強方法
学力検査を乗り越えるための勉強方法は、苦手分野は基礎を重視し、得意分野を伸ばすことです。
医学部の受験のような高得点が求められる試験では、他の受験生が正答する基本的な問題は絶対に間違わないようにしましょう。
得点できないと後れを取るリスクが高くなるため、苦手分野の克服は重要なポイントです。
しかし、不得意な分野で人並み以上の成績を収めることは難易度が高く、学習の費用対効果が悪化する可能性があります。
基本事項をしっかりと押さえ、基礎や仕組みの土台を整備した後は、得意分野の学習に専念する方が得点率アップに効果的です。
面接の勉強方法
面接を乗り越えるための方法は、想定される質問を把握し、明確な答えを準備することです。
〇〇大学の志望理由や医師を目指した動機、長所や短所など、一般的な質問が多く聞かれます。
また、最近気になったニュースやよかったことなど、面接と直接関係ないような質問が投げかけられる場合もあります。
日頃から医療関連のニュースや論文に接して情報収集をする習慣をつけておくと、想定外の問いかけにも理路整然と答えることができます。
また、面接は医師としてふさわしい人格を持っているかを確認する場です。
回答の際には、知識を披露するだけでなく、倫理的に問題ない回答かを慎重に考え、言葉にするようにしましょう。
小論文の勉強方法

小論文の効果的な勉強方法は、過去問に取り組み、出題傾向を把握したうえで添削を受けることです。
自分で客観的に、論理性の高いよい文章かどうかを見極めるのは難しいため、学校や塾の先生に依頼して手直しを受けることが上達につながります。
小論文では、問題文の趣旨に沿うことや、論理の飛躍がないことが重要です。
「自身の経験を踏まえて」とただし書きがある場合は、問いに関するエピソードを取り入れる必要があります。論理の飛躍とは、因果関係を説明する際に途中の要素を省略してしまう現象を指します。
このような論理的な文章を書くことに慣れていない方は、よく失敗します。数をこなして何度も添削を受けることで、書き方の癖をなくしていきましょう。
横浜予備校では、個別指導と小人数制(1クラス平均2名)を組み合わせた学習環境を整え、生徒一人ひとりの進度や課題に応じたきめ細やかなサポートを行っています。
特に、医学部の二次試験で重視される面接対策にも力を入れており、志望理由の深掘りや受け答えの練習など、実践的なトレーニングを通じて本番に強い対応力を養います。
学科・面接の両面から対策できる総合プランにより、合格に向けた準備を効率的かつ着実に進めることが可能です。
学習内容だけでなく、学習計画や費用面も含めてバランスよくサポートする体制が整っています。医学部二次試験に向けて、質の高い学びを求めている方は、ぜひお気軽にご相談ください。
医学部の二次試験対策を効率よく行い合格をつかもう

医学部の二次試験対策は効率のよい学習が求められます。なぜなら学力検査に加えて、小論文や面接の対策が伴い、忙しない状況に置かれるためです。
「医学部の二次試験対策に取り組みたいけれど、時間が足りない」と感じている方には、横浜予備校の学習環境がおすすめです。
一人ひとりの得意・不得意を踏まえた丁寧な指導を行い、1対1〜最大4名までの少人数クラスと個別対応を組み合わせたサポート体制を整えています。
医学部受験に特化した専用カリキュラムでは、学力対策に加え、二次試験で重要な面接や小論文対策にも対応可能です。
「二次試験の準備をどこから始めればよいかわからない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。