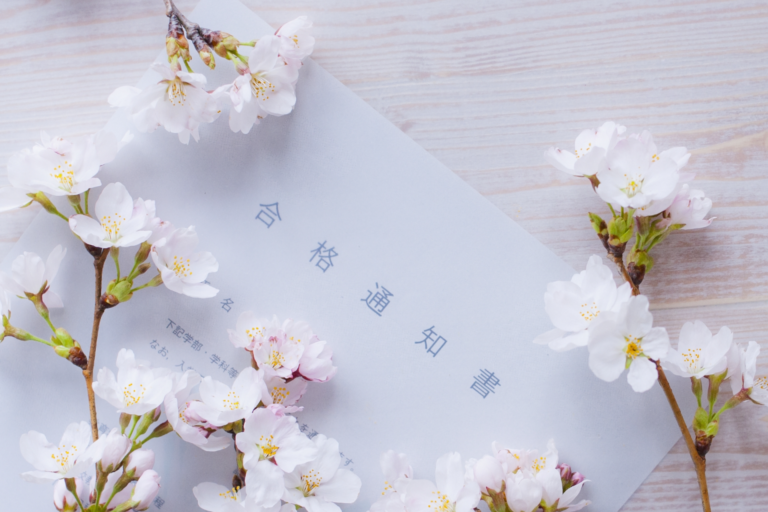東京医科大学入試問題『数学』2018攻略法|横浜の医学部予備校
現役の国立医大生に東京医科大学医学部2018年度の実際の入試問題を解いてもらい、
各問題の率直な感想をもらい、問題分析をしてもらいました。
受験生の立場に非常に近い現役医大生の感想なので受験生の立場に近い感覚だと思います。
是非、参考にしてください。このコラムが受験生の皆さんのお役に立てれば幸いです。
私大医学部の問題の入試分析と対策(2018年度、東京医科大学 数学)
(2018年2月3日実施)
・3教科で400点満点
・偏差値は67.5程度
・大問にして5つ、小問にして14問
・全問題マーク式での解答
・全体の難易度はやや易~やや難で、完答は難しいため解ける問題から確実に解いた方が得点は上がる
・技能・知識はセンター試験レベルのものと同等かそれよりやや難しい
以下、✩~✩✩✩で難易度を表します。
✩の数が増えるほど、難易度が高くなります。
第1問 ✩✩
この大問はベクトルをテーマにした問題で構成されています。他の大問と比べて全体を通しての難易度は高くなく、数学が苦手な人が得点したい場合は第1問や第3問を大切にするといいと考えました。センター試験レベルよりも少し難しい程度なので、ぜひ得点できるように対策をしっかりとしておきましょう。ベクトルはいくつかの作業の組み合わせですので、自身が与えられている情報を整理するのが苦手なのか、計算をするのが苦手なのか、絶対値や長さに変換する過程が苦手なのかを把握しながら解いて、後から苦手だと感じる過程を重点的に復習しておきましょう。
対策としては、Focus Goldやチャートの青・赤などで基礎的な部分の理解を分野ごとに深めて、クリアなどのような様々な大学の過去問を解きなれていくことがいいと考えられます。今回の第1問ではベクトルを使う問題の中でも比較的簡単なものだったので、基礎的な問題集で勉強できる部分で補えましたが、ベクトルという分野は問題を難しくしようと思えば思うほどいくらでも難しくできるので、他の大問が簡単な問題の時はベクトルを難しくして出題するケースも考えられますので、難易度の高い問題まで対策しておく必要はあります。
第2問
(1)✩✩ (2)✩✩✩
この大問では、極大・極小、微分、logを使って計算を進めます。難易度は第1問に比べて高いので、数学が苦手な人は他の大問(特に第1問や第3問)に時間を割いた方がいいでしょう。難しい問題のように感じる理由は、式の次数が高く、式が複雑であることが挙げられます。それを微分するとなるとかなりの注意力が必要ですが、計算ミスをするとマークする場所に当てはまらなくなるので、発見はしやすいでしょう。ですので、後からまとめてマークするのではなく、一つ答えが出たらマークしていくことでミスの早期発見につながります。
第3問
(1)✩ (2)✩✩✩ (3)✩✩✩
この大問は数列、Σの計算の理解が必要です。この問題の特に(1)の良いところは、書き出していけばいずれは答えにたどり着けるところです。第2問などと比べると時間をかければ正解できる可能性が高いです。書き出すのは非効率的なような気もしますが、テスト開始後に他の問題に目を通した際に、どの大問にならば時間をかけてもいいのか(すなわち、どの問題なら時間をかければ解けるのか)を基準に解く問題を選び、他に解ける問題が少ない場合は第3問に時間をかけましょう。
対策としては、多くの入試問題を解く事と数列に具体的な数字を当てはまる事です。数列は文字で表現されますが、具体的な数字を入れて計算することで数列の流れを把握することが容易になります。
第4問
(1)✩ (2)✩✩✩ (3)✩✩✩
関数とグラフ、それを用いた体積の計算をテーマとして大問です。難易度は高いようにも見えますが、よく出てくるタイプの問題ともいえるでしょう。頻出問題内容ですので、ここで得点できる受験生は比較的多いことが予想されます。あらゆる問題集でもこのタイプの問題が掲載されていますので、対策はしやすいと思われます。問題の解き方も決まっていますので、解き方を理解しておいてそれを再現できれば得点できたも同然です。とにかく最優先事項は解き方を暗記することです。そこから再現できるように何度も解くことで入試でも解ける問題になります。
対策としては、同じような問題を繰り返し解く事と、曲線を実際にイメージすることです。(1)、(3)は特に図形をイメージしてから解く事が重要ですので、実際にグラフの概形を書いてみたり、点をプロットして概形を考えてみることで立式しやすくなりますよ。
第5問 ✩✩✩
この大問には1つしか問題がなく、この問題がかなり複雑なのです。しかし、グラフを書く事のいい点としては、点をプロットしていけることです。点を書き込んでプロットしていくことでグラフの特徴や概形を知ることができるため、時間をかければ答えにたどり着かないことはないです。ただし、解答にあたって指示がありますので、それを必ず守るようにしましょう。時間が余っているときになら時間を割いてもいい問題と言えるでしょう。
2018年度の東京医科大学入試を、完璧に解ける人はかなり少ないように感じます。特に数学は難易度も高く、解き方が複雑なものも多いですので、「自分はどの問題なら解けるのか」ということを見極めてから取り掛かることが望ましいです。時間をかけてでも確実に得点できるところから進めることで少しでも得点アップが望めます(今回は第1問や第3問といったところでしょうか)。どの問題も良く出てくる出題形式ですので、間違えたところは解説をしっかりと読んで模範解答の方法でも解けるようにしておくことで、次からはより短時間で解けるようになります。同じ大学であれば好んでいる解き方や分野はありますので、入試本番でも模範解答の解き方は役に立つ可能性は高いです。ぜひその視点で過去問を分析してください。
制限時間と問題の難易度を考慮すると、解く順番が重要になりそうです。個人的には第1問、第3問、第5問、第4問、第2問の順で解きます。このような順番にした基準としては、確実に得点できそうだと感じたものから解き、その中でも時間がかからなそうなものから優先的に解きました。もちろん、得意な分野不得意な分野は人によって様々なので、自分の中で解く順番を決められればいいです。ただし、決める際の基準は「確実に得点できるか?」「短時間に解くことができるか?」になりますので、テスト開始後にはまず全体に目を通してどの問題から解くかを瞬時に判断しましょう。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
住所:神奈川県横浜市中区花咲町1丁目18番地
第一測量桜木町ビル5F
TEL:045-250-3915
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇